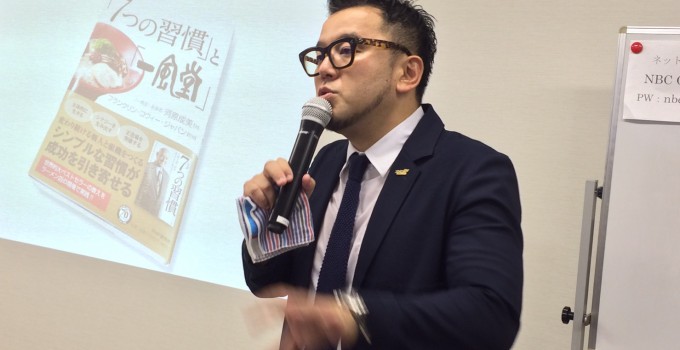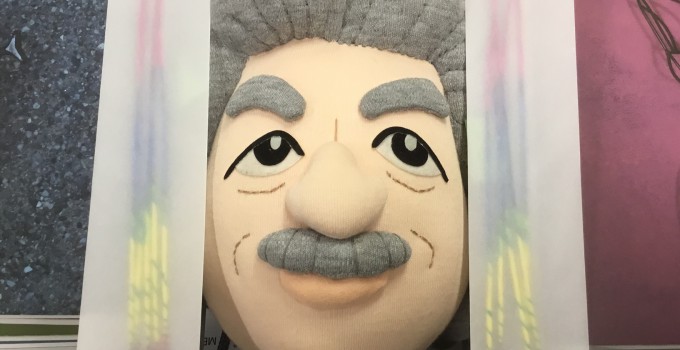12/11
2017

ウシの上にも3年!
タイトルを見て
「なぜウシ?」と思った方も多いだろう。
そう、今回の話は「石の上にも3年」ではなく
「ウシの上にも3年」なのだ。
現在、
北海道で展開しているMemuroワインヴァレー構想。
地域の農家や企業と一緒になり、
様々な企画を進めている。
その中の一つに、酪農家とのチーズ工房がある。
この酪農家は400頭もの牛を飼育しており、
北海道の中でも大きな酪農家だ。
さらに、その生乳の乳脂肪分は4.3%と、
全国平均3.9%を大きく上回る品質なのだ。
なぜ、これほど高い脂肪分を保てるのか。
その背景には、この酪農家親子の
「本当に良いものを作りたい」という、
数年間にわたる戦いがあった。
一般的に、牛を育てるための餌には
“粗飼料”と“濃厚飼料”の2種類がある。
ほとんどの酪農家が、
デンプンやタンパク質を混合した濃厚飼料を使っている。
この親子も、当初は農協で勧められる
輸入品の濃厚飼料を使っていた。
それは輸入にたよった展開であり、
コストもかかる不安定な事業となっていることから、
「本当にこれで良いのだろうか?」と考えたのだ。
そして、牛本来の生態系に沿い、
牧草中心の粗飼料に切り替えようと決めたのである。
ところが粗飼料を使い初めると、
なんと400頭のうち100頭あまりが次々と死んでしまったという。
濃厚飼料で育った牛たちの胃袋は、
牛本来の反芻胃が機能せず
牧草の消化に対応し切れなかったのだ。
(牛には胃が4つあり、本来は耐えられるようになっているのだが…)
親子は、時にお互いを責め、ぶつかり合いながらも、
諦めず試行錯誤を続けた。
そうして数年かけて粗飼料に切り替えていった結果、
脂肪分4.3%という、高付加価値の生乳に至ったのだ。
この話を聞き、
ふと木村秋則さんの「奇跡のリンゴ」を思い出した。
木村さんは、無農薬のリンゴを育てようと、
11年もの間、不作に耐えて研究を続けた。
まともなリンゴができるまで
15年はかかったというからスゴい忍耐。
やはり、何事も一朝一夕には成し得ないのだ。
今までの“あたりまえ”を大きく変えるというのは、
とてもパワーがいること。
それは私たちのビジネスでも同じではないだろうか。
挑戦すると決めたなら、
起りうる困難にも覚悟を持ち、
忍耐していくことが大切なのである。
これこそ、まさに石の上にも3年…ではなく、ウシの上にも3年だ!!
(この生乳で作るチーズは、きっと一味違ったおいしさになるだろう…!
今からワクワク…!)