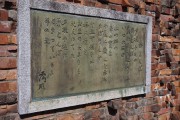05/29
2017
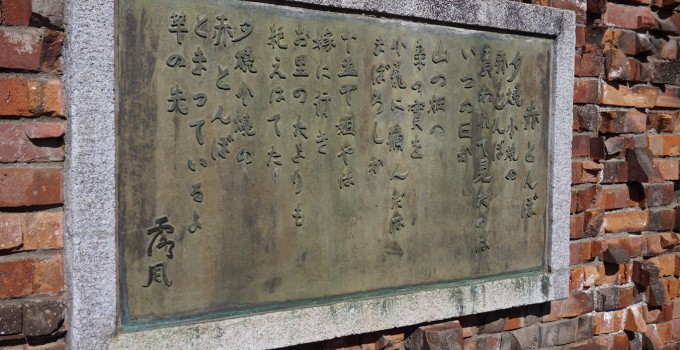
歴史、文化を活かしたストーリー性
夕焼け小焼けの赤とんぼ
負(お)われて見たのはいつの日か
誰もが一度は聴いたことがある『赤とんぼ』。
作詞が三木露風、作曲は山田耕筰による日本の代表的な童謡だ。
実は三木露風は兵庫県たつの市出身。
先日「日本を美しくする会」の企業見学会で、
たつの市を訪れたときにこの『赤とんぼ』の歌詞を見かけた。
一緒にいた人は、それを見て初めて
「おわれて」という歌詞が「追いかけられて」ではなく
「背負われて」という意味だと気付いたという。
私も仕事柄、いろんな地方にいくことがあるのだが…、
やはり日本はどこに行っても、
その土地ならではの歴史であり文化を知ることができる。
他にもたつの市といえば、
そうめんブランドの「揖保乃糸(いぼのいと)」が有名だ。
なんと手延そうめん全国シェア40%を誇っているのだとか。
市の歴史をみると、1418年に書かれた寺院日記の中に
すでに「サウメン」という記述があるという。
(つまり600年も歴史があるってこと!)
やっぱりストーリーを知って食べると、
よりその美味しさを感じるよねぇ~。
そして、私が見学先の手土産に持参した新正堂の「切腹最中」。
新橋のもともとのお店の場所が、
忠臣蔵で有名な浅野内匠頭が切腹をした場所とのことから
現店主(渡辺仁久氏)が発案した商品なのだが…。
実はたつの市は播磨赤穂藩があった場所。
つまり赤穂浪士の地元だったのだ!
いまや1日に4000個を売り上げる人気商品との予期せぬ
つながりには驚いた。
さらに隣市にある、1346年に建立された世界文化遺産で
国宝の姫路城も見学した。白鷺城とも称される美しいこの城は、
いまや年間280万人を超える日本一の入城者数を誇っている。
さて、ここで私が語りたいのは、
たつの市周辺には観光名所がたくさんあるということではない。
「日本を美しくする会」の企業見学会でたまたま訪れた
兵庫県たつの市だけでもこんなに歴史や文化を知り、
ストーリー性を感じることが出来たってこと。
だから、先ほど紹介した「揖保乃糸」にも「切腹最中」にも
姫路城(白鷺城)にも、固有のストーリー性があり、
多くの人たちから選ばれるものとなっている。
そこにスト-リー性があるからこそ足を運ぶ。
そのストーリーがクチコミで広がる。
そしてブランディングが確立する。
やはり、これを活かさずして、
ビジネスは活性していかないのではないか。
すなわち、ストーリー性を持たせることこそ、
多くの人たちが耳を傾け、興味を持ち、
結果として選ばれる理由になるということなのだ!