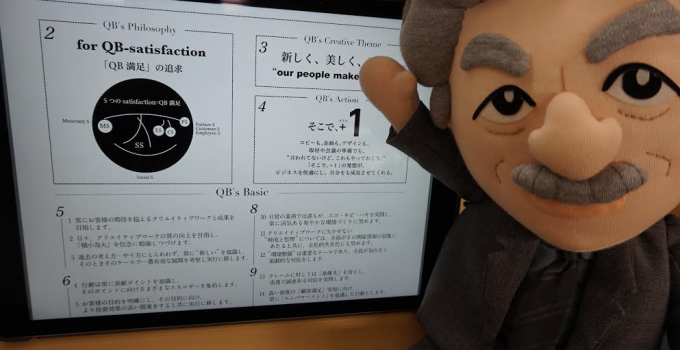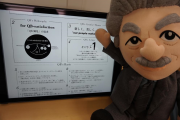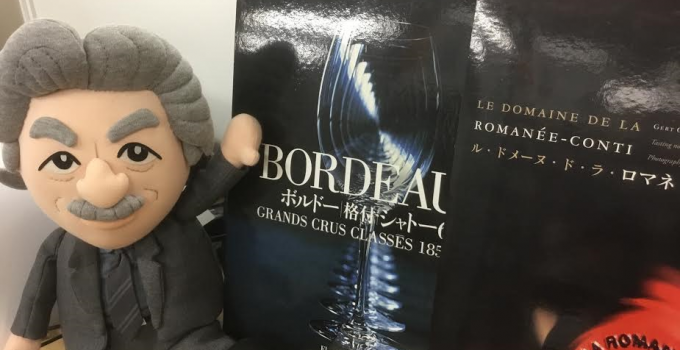07/11
2016

これがボルドーシャトーのプライド
門を入って眼前に広がったのは美しく整備された庭。
その向こうには、どこまで続くのか? と思わせる
ワインぶどうの並木。
そして、歴史を感じさせるシャトーの建屋の中には
千を超す樽が整然と並べられていたのだ。(スゴーイ!)
ここは、ボルドーに入って最初に訪問した
シャトー・パプ・クレマン。
お~、これが本場のシャトーということか、
なんて思ってしまった。
次に向かったのは、シャトー・オー・ブリオン。
一級シャトーである。
このシャトーにも、美しく整い品格のある庭が広がり、
昔ながらのまさにシャトーという雰囲気があった。
さらに、シャトー・マルゴー
(途中で二手に分かれたため、
私は残念ながらいけなかったのだが…)。
そして最後にサンテミリオンの
シャトー・フォン・ブロージュ。
ここでも庭は完璧に整備されていたのだが、
さらに、庭の中央には17世紀に使われていた日時計が…
歴史の長さと、確かな格を感じたのだった…。
ご存知の通り、ボルドーのシャトーは
1855年の第1回パリ万博で
当時の評判や市場価値に従い、
初めて格付けが公式に決定された。
だが、その以前からすでに、
選ばれるシャトーには
純然たる差があったのだろう。
つまりすでに、選ばれるシャトーは
いいワインをつくるため、
するべきことを実践していたということだ。
そしてそれから160年以上のあいだも、
それぞれのシャトーは、その格付けを維持しようと
手間のかかる方法でも徹底して
実践してきたということだろう。
そんな各シャトーのプライドが、
門を入った瞬間、目の前に広がる
あの隅々まで整備された庭に表れていると
私は感じたのである。
どのシャトーも、庭だけではなく、
建物、樽、貯蔵室、
シャトーの建屋自身も徹底して美しく、
その美しさを次代に繋げようという意思が感じられた。
そんな意思こそが、注目される上位ワイナリーとしての
自負であり、プライドなのだ。
ワインの世界から少し離れるが、
老舗・虎屋の17代当主黒川光博氏の
「伝統とは革新の連続である」という言葉。
虎屋の490年はさまざまな試行錯誤であり、
革新の連続だったということだ。
なぜか、これらボルドーのシャトーを訪問していて
この言葉が頭に浮かんだのだ。
実はシャトーも、そのぶどうづくりや醸造の仕方には
その時代その時代のトレンドがあり、
ず~っと試行錯誤を繰り返してきたという。
すなわち、シャトーも虎屋と同じく
ここ200年は革新の連続だったのではないかと思うのだ。
格付けによる品質をも保つための様々な試行錯誤が、
結果としてあの美しい庭に表れているのだろうと、
シャトーの庭を脳裏に浮かべながら思ったのだった…。