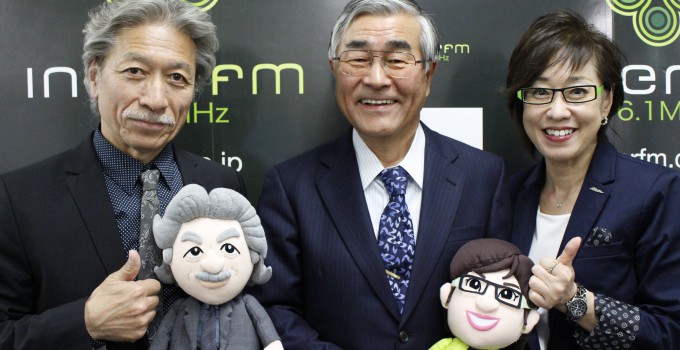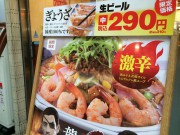06/01
2015

「選択と集中」が選ばれる
目的意識を持たず、まんべんなく行動すると、
明確な目標にたどりつきにくくなってしまう。
その結果は、ビジネスでは特に顕著に現れる。
以前ここでもお話した、アメリカで「Small Giants」と
称されるある中小企業の話。
その企業は、10州以上にまたがって幅広く
ビジネスをしていたのだが、
このままではいいサービスができないと
力を入れるポイントを3州に絞り、
その他の州のお客様をライバル会社に譲ったという。
それによって力を入れた州のお客様の満足度が高まり、
より多くの人々から注目が集まるようになったという。
これはアメリカに限った話ではない。
日本でも私の知るところの企業では、
あのフォルクスワーゲン社ビートルの
オリジナルパーツを製造販売する
株式会社フラットフォーがその例だろう。
あのカブトムシ型と呼ばれるビートルに特化し、
その関連商品だけを取り扱ったことで、
世界から注文が殺到する会社となったのだ。
一見すると偏って見える力の入れ方が、
特徴というノウハウを持ったオンリー企業となり、
多くのお客様から指名される企業。
このことは、会社だけではなく、個人にも当てはまる。
最近よく耳にする「ワークライフバランス」という言葉。
まんべんなく働き、プライベートな時間も
充実して過ごすということは、
当然生きるうえでは悪いことではない。
しかし、ある業界で働くプロフェッショナルとしての
視点で考えると、それではいい仕事はできないし、
選ばれる人にはなれない。
その道で選ばれる存在になるためには、
限られた時間をどう“アンバランス”に
使っていくかが鍵になるのだ。
自分の知識やノウハウ、スキルを
徹底的に向上させるなら、
普通の時間の使い方では突出した成長は期待できない。
時には、寝る間も惜しんで自分磨きに勤しみ、
プロフェッショナルとして高みを目指していかなくてはならないのだ
(これをやっとかないとある程度年齢を重ねてから大変だからね~)。
こうした考え方は、中小企業も一緒。
中小企業のほとんどは、大規模経営でないため、
世間的にまんべんなく大きな影響を与えることは難しいからだ。
では、その中で選ばれるには
どうしたらいいのだろうか。
先ほどのフラットフォー同様にキーワードは
“選択と集中”なのだ。
あの中里スプリング製作所は、
「町工場」という小規模経営に徹することで、
バネづくりに注力した。
そして全国各地のメーカーにとって欠かせない役割を果たす企業としての
存在理由を手に入れたのだ。
石坂産業も同様だろう。「産業廃棄物の処理」という
広い事業範囲ではあるが、そのリサイクル率に注力し、
地域からも喜ばれる企業として存在することに焦点を絞った。
すると多くの視察者が訪れる企業となったという。
どのポイントに絞り、その技術力と人材を集中させるか。
これは経営者の決断ということだろう。