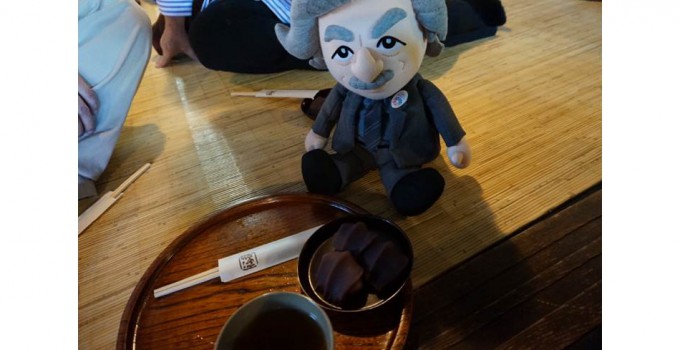10/27
2014

“とみひろ流”ビジネスの仕掛け
「私は毎日会社周辺を30分ほどですが、掃除しています。
冨田社長はどのくらい掃除しますか?」。
山形掃除に学ぶ会代表世話人であり、
山形の老舗呉服屋「とみひろ」の社長・冨田浩志氏に
尋ねると驚きの答えが返ってきた。
「私は、毎日3時間ほど掃除しています」。
なんと、3時間とは…!
しかも冨田氏は10数年間継続しているというから驚きだ。
掃除時間もさることながら、創業から23代目の冨田氏は、
ビジネスでのチャレンジ精神も素晴らしい。
冨田氏が経営する「とみひろ」は呉服業であり、
業界的には厳しいのだが、その中でも様々なチャレンジをしている。
山形に本店を置く「とみひろグループ」なのだが、
東京をはじめ、埼玉、宮城、そして京都にも支店を出店。
また、より多くの“着物の機会”拡大のために、
今年の夏には、青山のショッピングモールにて浴衣イベントを開催して、
500人を超す浴衣姿のお客さんを動員したという。
さらに、その挑戦はさまざまな関係分野に発展している。
仙台では人生の節目を着物で演出する写真館を運営し、
多くのお客様に喜ばれているという。
また、地元山形では明治時代に建てられた蔵を活用して、
クラシカルウエディングを挙げることができる結婚式場を構えている。
一方で、マーケティングや事業展開にも余念がない。
京都の支店では販売を目的にせず、
旬の着物や全国メーカーの問屋などから直接仕入れをしたりして、
さまざまな情報を収集しその情報を活かして開発もしているという。
数百年続く「とみひろ」だが、こうした数々の仕掛けを見ると、
もはや23代目の冨田氏が第二創業期と言っても過言ではないだろう。
そして、そのチャレンジは日本の中だけにはとどまらない。
なんと今は、ロンドンにもオフィスを置いているのだ。
そこではヨーロッパ各地で開催されている展示会に参加し、
日本の着物文化を発信しているそうだ。
冨田氏は、こうしたすばらしいチャレンジを数々している。
老舗呉服屋「とみひろ」は、次の時代を見据えて、
着物文化の可能性を模索し、次々にビジネスを拡大しているのだろう。
そんな、ビジネスのヒントになる冨田氏の
エピソードはまだまだたくさんある。
InterFMにて11月2日(日)朝6時から放送の
『BUSINESS LAB.』をお楽しみに!