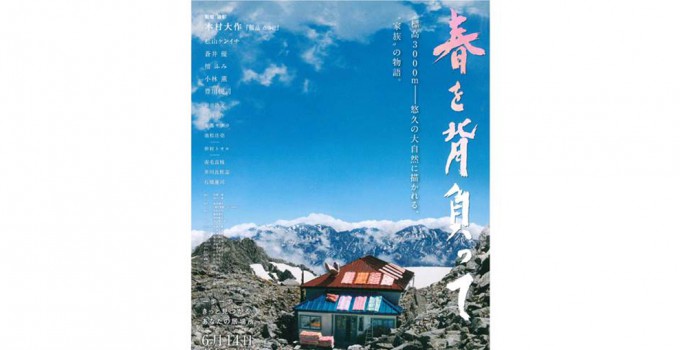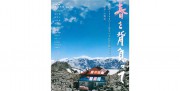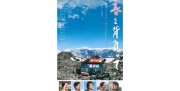03/03
2014

新川義弘CEOのポリシー
『飲食店はエンターテインメントの場』。
そう語るのは、都内を中心に
18店舗ものレストランを展開している、
株式会社HUGE(ヒュージ)の
代表取締役CEO新川義弘
(しんかわ・よしひろ)氏。
新川氏といえば、
2002年の日米首脳会談において、
ブッシュ大統領夫妻と小泉首相の
会食のサービスを担当したことで有名だ。
そんな新川氏の“選ばれるビジネス”
を象徴するのが、先ほどのフレーズ
「飲食店はエンターテインメントの場」
という価値観。
すなわち、新川氏にとって飲食店とは、
ただ料理を提供する場所ではない。
最高のエンターテインメント空間、
また普段とは違う非日常空間を
提供する場所ということだ。
例えば、私中島も
何度か利用させてもらっている、
銀座の高級(?)イタリアン
『DAZZLE(ダズル)』。
エレベーターで昇り、
8階のエントランスで
まず目に飛び込んでくるのは、
なんと活気に満ちた
オープンキッチンなのだ。
「降りるフロアを間違えたのかな…」
いや、そうではない。
最初に調理場の活気やシズル感を
見ていただくことも、
新川流の空間演出の
ひとつなのだという。
そして、そこからまたひとつ
上のフロアに昇ると、
そこには吹き抜けの
天井の高さを活かした、
ブリリアントカットの
ワインセラーが姿を現す。
このDAZZLEのシンボルとも言える
巨大ワインセラーは、
お客様の驚きを生むと同時に、
“記憶”に残ることは間違いない。
また聞くところによると、
代官山にある人気店には
1万4千のクリスタルピースが
あしらわれた豪華な
シャンデリアもあるそうだ。
つまり、どのお店も
遊びの空間やユニークなシンボル、
そして上品でありながら
どこか粋な演出がある。
それは、まさにお客さまにとって
“記憶”に残るエンターテインメントなのである。
しかし、新川流のお店づくりは
それだけではない。
新川氏曰く、レストランは
“総合商品”なのだとか。
すなわち適正な価格、料理、
空間演出、そしてサービス。
どれも手を抜いてはいけない
大切な要素だという。
特に「サービス」に関しては、
他の要素よりも高い
プロ意識が感じられる。
営業時間外を使って行われる、
従業員たちによる
接客ロールプレイングの実施が
その証といっていいだろう。
目指すは、お客様がしてほしいと
思っていることを事前に察知し、
お客様が口にする前に
サービスを提供すること。
それこそが新川流サービスの
基本であり、サービスの全てなのだ。
『エンターテインメントの空間×総合商品』。
それそこ新川氏のポリシーであり、
多くのお客様やその地域に
長年選ばれ続けている
存在理由なのだろう。
そんな新川氏がついに
InterFM『BUSINESS LAB.』に登場!
3/9、16は是非とも新川氏の
エンターテインメント性を
感じていただきたい。
――――――――――――――――――――――
InterFM『BUSINESS LAB.』
東京76.1MHz・横浜76.5MHz
毎週日曜 朝 6時から好評放送中!
──────────────────────