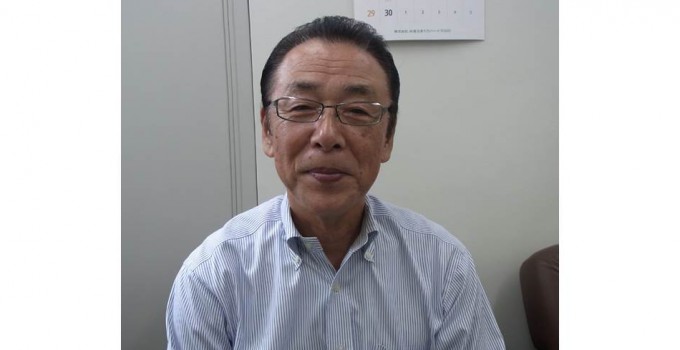10/28
2013

難(かた)きを先にし、獲(う)るを後にする
「難きを先にし 獲るを後にする」
により“仁”が得られるとし、
「事を先にし 得るを後にする」
ことで“徳”が高まる。
遡ること2500年前、孔子が語ったとされるこの言葉は、
難しい仕事を自ら進んで引き受け、
利益を得るのは後回しにするということ。
これは私がよく口にする「先義後利」
(拙著にも登場する言葉)の
元になっている言葉だとも言われている。
そして、私がパーソナリティを務める
『BUSINESS LAB.』に出演していただいた
起業家のみなさんが、まさにそれを体現しているのだ。
まず、サムライインキュベ―トの
CEOである、榊原健太郎氏。
70社のベンチャー企業を相手に、
ビジネスモデルのブラッシュアップの他に、
経営のノウハウや金銭面での支援まで行っている。
この支援はあくまで将来のための投資ということ。
次にユーグレナの出雲充社長。
これまで誰も成功しなかった、
ユーグレナ(ミドリムシ)に注目。
周りから「無理だ」と言われていたにも関わらず、
あきらめないで研究を続けた。
すべてを集中して覚悟を決めての
チャレンジが成功を引き寄せたともいえる。
そして、今週放送予定の、
アスカネットの福田幸雄社長。
専門知識のない葬儀会社のスタッフが、
専用機器に写真を置くだけで、
遺影づくりのオーダーに
対応できるシステムをつくり上げた。
しかし、この事業を発想してから
実際にビジネスとして展開できるまでには、
実に5年もの歳月がかかったという。
福田社長はさらにオリジナルフォトアルバム事業も、
5年の歳月と毎年1億円ほどの資金を投資した結果、
他の追随を許さないブランドを
しっかりつくりあげることができたのだ。
これらの人たちはまさに
「難きを先にし 獲るを後にする」を
実践してきた人たちと言えるだろう。
これからのビジネスは、これまで以上に
リスクの少ないビジネスなどないのだ。
覚悟してチャレンジするかどうかが、
そのビジネスをものにするかどうかの分かれ目だろう。
それにしてもアスカネットの福田社長は試行錯誤しながらも、
しっかり“高み”に上りつくところがスゴい。
実は福田社長、次なる新たなビジネスでも“高み”を目指しているという。
さて、どんなビジネスなのか。
この話の続きは、11/3と11/10放送の『BUSINESS LAB.』で聴いてもらいたい。
──────────────────────
InterFM『BUSINESS LAB.』
東京76.1MHz・横浜76.5MHz
毎週日曜 朝 6時から好評放送中!
──────────────────────