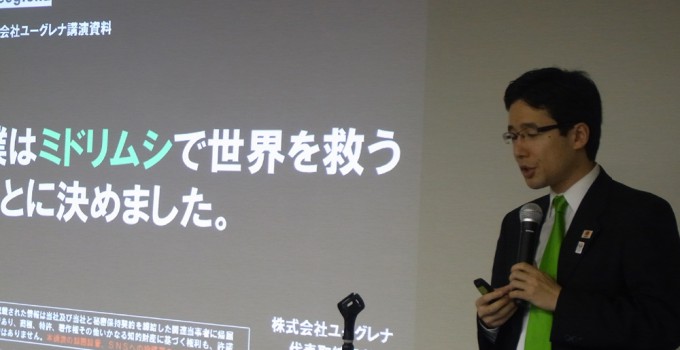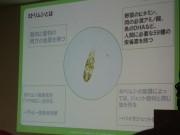07/08
2013

あのホールフーズが“増収増益”
「ホールフーズが増収増益!」
先日、新聞でこんな記事を発見。
健康をテーマとしたグルメスーパー(?)である、
アメリカのホールフーズが、増収増益したというものだ。
四半期決算で、売り上げ13.3%増、利益20.3%増という数字は、
売り上げ1兆円規模の大手スーパーにおいて
異例の好業績を記録したことになる。
ホールフーズといえば、先のニューヨーク・シカゴツアーで訪問し、
インタビューさせていただいたお店。
ここでは、オーガニック食品を取り扱い、
“全米で最も健康的な食品スーパー”という言葉を掲げ、
300店舗以上も展開している。
先日紹介したトレーダージョーズにしろ、ホールフーズにしろ、
感じたのは他のスーパーマーケットとは
一味も二味も違うということ。
ここで鍵となるのは、
ホールフーズの創業者である現在59歳のジョン・マッキー氏。
思えば、ホールフーズは1980年創立という、
比較的若いスーパーマーケットだ。
それが300店舗を展開するに至るまで
急成長できたのはなぜだろうか。
まずホールフーズは、当時まだそれほど浸透されていなかった
オーガニック食品の専門店として登場する。
それは次第にアメリカで受け入れられ、
マクロビオティックという価値観を広めるのに一役買った。
これを受けて、事業を拡大するため大型の高級グルメスーパーを目指すのだが、
2008年のリーマン・ショックで事態は急変、
苦しい局面を迎えることとなった。
そこで、ジョン・マッキー氏は決断する。
ターゲットを富裕層ではなく、健康志向のより多くの人々とし、
彼らの需要に応えられる工夫をしよう、と。
そして、トレーダージョーズなどでも扱っているような、
1ドル99セントのワインなどの低価格商品も
しっかり扱うようにしたのだ
(これはトレーダージョーズをライバル視?)。
この結果、冒頭にあげたような、
1兆円規模のスーパーでは、いまやなかなか実現できない
大きな利益を上げることにつながったのだろう。
まさに、時代を先読みしたジョン・マッキー氏の
絶妙なタイミングで下した決断が功を奏したのだ。
そんな急成長を遂げたホールフーズは現在、
アメリカの「働きたい会社ベスト100」の上位に位置している。
現地で私がホールフーズのスタッフに
ジョン・マッキー氏について話を聞いたところ、こう答えた。
「私たちは、ジョン・マッキーを尊敬しています。
マッキーも私達を尊敬してくれています」
ジョン・マッキー氏の、時流をとらえ決断する力もすごいが、
経営者とスタッフとの信頼関係も
企業の成長に大きく影響していることが理解できる。
やはり、多くの人達から選ばれるのには、必ず理由があるということだ。
それにしても、こんなに注目される
ホールフーズやトレーダージョーズを
訪問先に選ぶセンスはさすが…と誰かが言ってくれている?