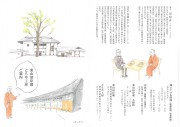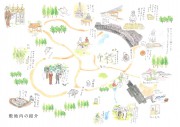04/01
2013

ローカル“十勝バス”のチャレンジ
日曜朝6時、あなたのビジネスは“選ばれるビジネス”へと進化する!
え? なんの話かって?
実は私がメイン・パーソナリティを務めている
ラジオ番組「BUSINESS LAB.」が、リスナーの熱いご要望にお応えして、
放送時間を日曜朝6時~7時へ変更したのだ。
その記念すべき第1回目のゲストは、北海道・帯広市に事業展開している、
十勝バス株式会社の野村文吾社長。
30数年間赤字経営が続いていた十勝バスを、
黒字経営にしたことで、以前ビジ達でも紹介させていただいた。
こんな実績を持っている野村社長だが、
父である先代の後を順当に継いだわけではなかった。
後を継ぐと決めた時に、先代からこんなことを言われたそうだ。
「お前にできるわけがない。自分で責任をとれるなら好きにやれ。
そのかわり、支援も手助けも教えもしない。」
本当に何のアドバイスも手助けもなかったという。
それだけではなく、なんと経営状況が赤字だということすら
知らされていなかったとか…。(え~!)
社長に就任してからも、いろいろと手は打つがうまくいかず、
社員との溝も深まるばかり…。
そこで、経営者仲間からアドバイスされたことを実践しようと決断。
翌日、幹部を集めて“これからみんなのことを好きになる”と宣言した。
この宣言から、少しずつ少しずつ、
従業員との関係も改善されて行ったという。
お客さまにとって、社員にとって「一番よい方法はなにか」を
トップダウンではなく、ボトムアップ型で一緒に考え、
そしてその意見・アイデアを反映した“KAIZEN”を展開して行った。
すると、社員の目つきがだんだん柔らかくなり、
信頼関係も築くことができたという。
このように、様々な困難を乗り越え赤字経営を克服していった野村社長。
まさにアサヒビールの立役者・樋口廣太郎氏の言葉
“挑めばチャンス、逃げばピンチ”そのものである。
困難を乗り越えるたびに、
経営者は成長すると言っても間違いないだろう。
…というわけで、ここまで読むと、
さすがに野村社長の話をもっともっと聞きたくなったはず。
詳しいお話は4月7日・14日、日曜朝6時の「BUSINESS LAB.」で!
日曜の朝、あなたのビジネスが変わる…!
──────────────────────
InterFM『BUSINESS LAB.』
東京76.1MHz・横浜76.5MHz
毎週日曜朝6時から大好評放送中!
──────────────────────