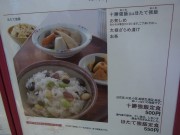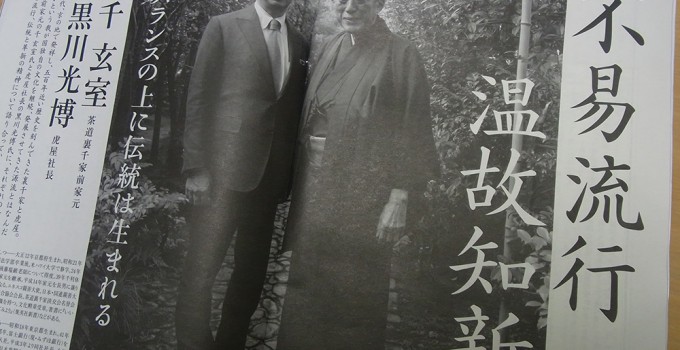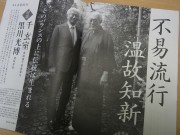02/04
2013

配慮という実践知
先日、山梨県の石和温泉で掃除の会・関東ブロック会議が行われた。
会場は最寄り駅から徒歩15分ほどの場所にある健康ランド。
たまたま電車の中で会った掃除関係者と
歩いて会場へ向かうことになったのだが、
線路に沿ってしばらく歩いていくと、前方に線路にかかる大きな陸橋が…。
地図を見ると、どうやら健康ランドはその陸橋を渡った先にあるようだ。
その陸橋を渡るべきかどうか悩んでいる時、
同行した方が近くで作業していた
おばさんにこう尋ねた。
「すみません、この道を上がっていくと線路の向こう側に渡れますか?」
すると、地元のおばさんはこう答えてくれた。
「渡れますよ~。あ、もし健康ランドに行くなら、
陸橋を渡るよりも左の道を行った方が
楽に行けますよ」。
え~、何で私たちが健康ランドに
行くと思ったのだろう…。
あのおばさんは私たちの
「線路を渡りたい」というその先にある、
「健康ランドに行く」という本来の目的を察し、
気の利いた答えをしてくれたのだ。
ビジ達でも紹介し、私がいま特に
着目している言葉、“実践知”。
マニュアル化や数値では表せない
知識や知恵のことなのだが、
この配慮もまた実践知であると言えるだろう。
こうした出会いや、以前ビジ達でも
紹介した北海道の居酒屋での
素晴らしい対応“ほっけの配慮”を受けてこんなことを感じている。
システム化されマニュアル化された
現代のビジネスにおいて、
お客さまはこれらの人間味のない現状より、実践知の活きたビジネスを
展開している会社を選ぶのではないだろうか、と。
実は、この実践知は日本に限ったことではない。
ニューヨーク郊外にある、世界No.1の
食品スーパーと言われている、
スチューレオナード近くのアイスクリーム店でのこと。
店員さんが金髪美女だったこともあり、
アイスを注文。
細かい硬貨の値が分からなかったこともあり、
美人の店員さんにポケットに入っていたお金を差し出した。
すると、どうやら端数の硬貨が足りなかったようで、
一瞬困ったような顔をしたのだが、
近くに置いてあったカップから数セント取り出し、
「No Problem!」という言葉とともに笑顔でアイスを渡してくれた。
こうした人の心に残るようなマニュアルにない展開や配慮の実践知こそ、必ずや多くの人の心を掴み、口コミ効果を上げ、ひいては選ばれるビジネスにつながっていくのではないだろうか。