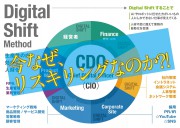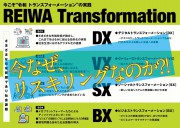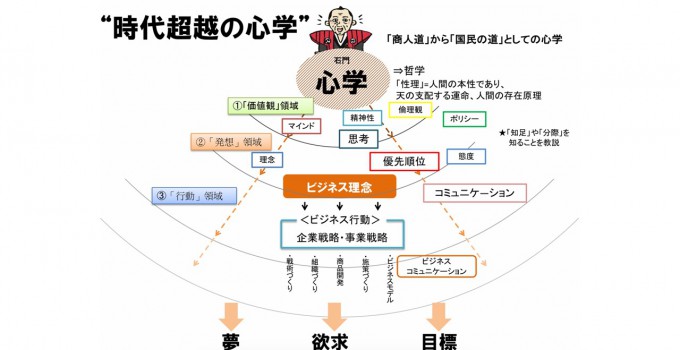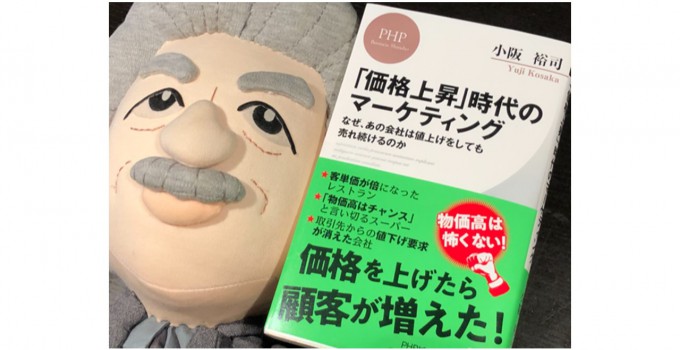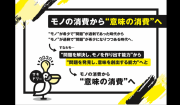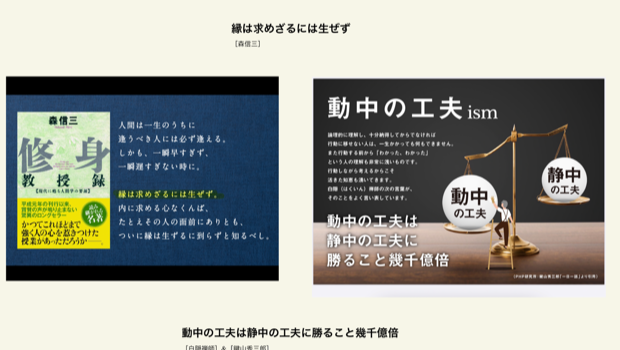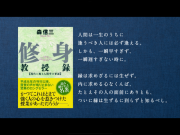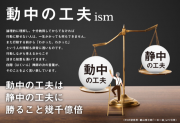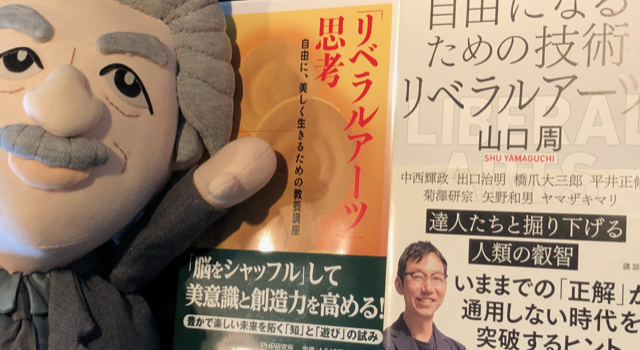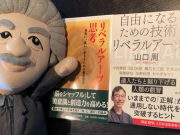11/28
2022
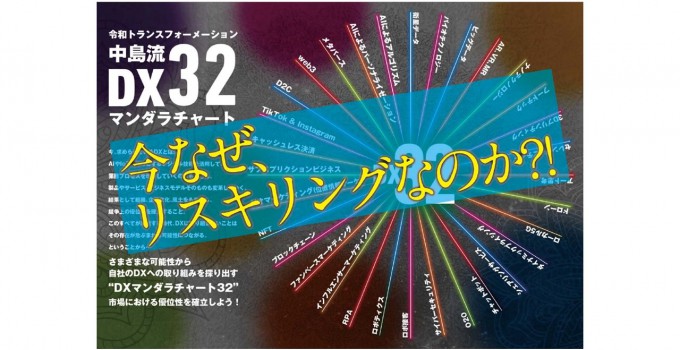
今なぜ、“リスキリング”なのか?!
今、注目の言葉“リスキリング”。
ご存知だろうか。
企業の経営者やリーダーにとって重要なキーワード
になっている。
“リスキリング”とは、直訳すると、
“スキルの再習得”や“職業能力の再開発”となるが、
新しいことを学び、新しいスキルを身につけ実践し、
そして新しい業務や仕事に就くことである。
それまでと違うスキルやノウハウの習得であり、
その後の業務や違う仕事につくところがポイント。
実は、2020年のダボス会議(世界経済フォーラムの年次総会)で、
「リスキリング革命」が主要な議題にあがった。
なぜ、“リスキリング”が必要かと言うと、
その世界経済フォーラムにおいて、
→2025年までに企業は6%の人員削減が必要
→従業員の2人に1人はリスキリングが必要 (主にデジタルスキル転換)
→これに該当しない半分の従業員も、自分が持つ40%のスキルを
変化する市場に適応させることが必要…とのこと。
これからの時代は、“技術的失業”と呼ばれる
テクノロジーの導入によりオートメーション化が加速し、
あらゆる現場において人間の雇用が失われる社会的課題が
深刻になってきている。
米国においては、
今後10年から20年の間に総雇用者の約47%の仕事が
自動化され消失するリスクが高いと言われている。
もちろんこれまでと違う新しい仕事の需要も増えるわけだが、
当然求められるスキルやノウハウは違ってくるわけだ。
例えば、第4次産業革命にはバイオ革命やロボティクスなど
様々な技術の変化が含まれるが、
なかでも注目されるのはやはりDXの加速になるだろう。
岸田総理もこの10月の所信表明演説内で、
リスキリングに“今後5年間で1兆円投入”いう発言をした。
これまでこの“ビジ達”では、
DXの重要性をあらゆるビジネス関係者に発信してきた。
この“リスキリング”は、まさにそれの実践のための
具体的アクションということ。
企業として取り組む責任もあるし、
取り組まないと、“すでに淘汰される側にいること”
と伝えたいのだ。
企業が“リスキリング”の推進によって、従業員に学びの機会を提供し、
キャリア形成の支援をすることは、
“ワーク・エンゲージメント”
(仕事に対してのポジティブで充実した心理状態のこと)
の向上にもつながる。
そうすると生産性は向上し業績にも貢献する。
従業員のなかにも自分で新しいスキルを獲得しよう
という風土が生まれる。
自発的に考えられる「自律型人材」が増えることで、
ひいてはイノベーティブな組織に変わる
きっかけともなるのだ。
“リスキリング”の必要性を学ぶだけでなく、
まずはアクションを起こそう!