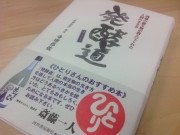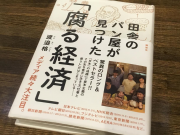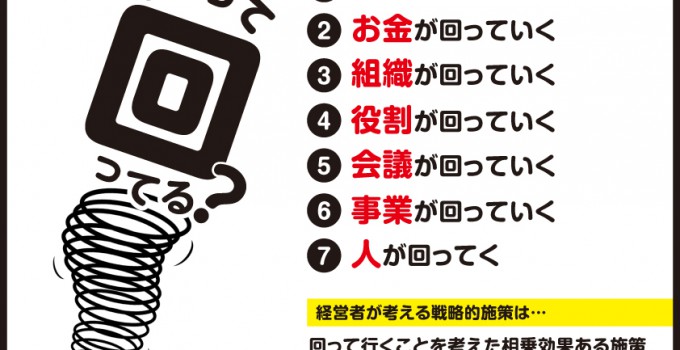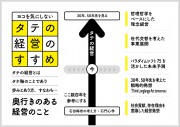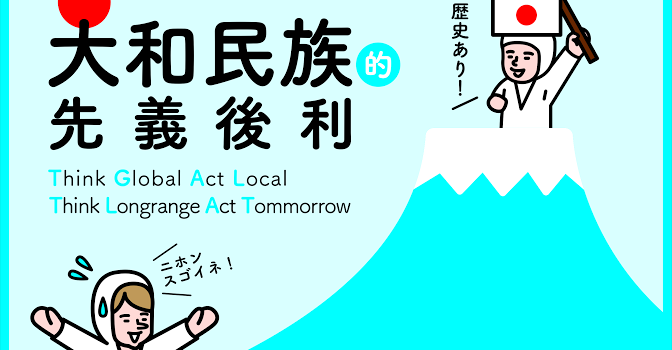08/29
2016
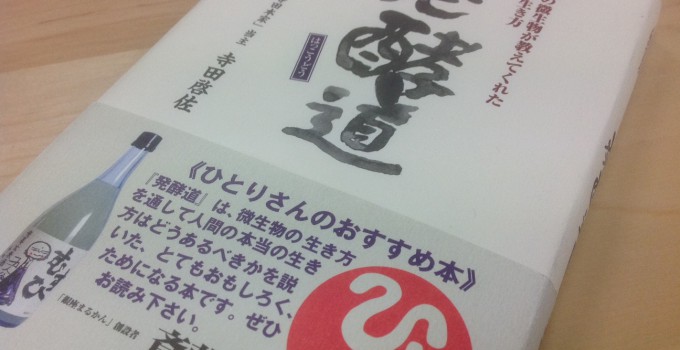
朱に交わればシンクロニシティ
弊社で毎月開催されている「石門心学・実践講座」で、
世話人をやってもらっているプラスソフトの竹花氏。
ある日、私に合った本とのことで1冊の本をいただいた。
それが渡邉格(いたる)著
『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』という本。
読んでみると、拙著『儲けないがいい』と
価値観が重なっているように思える内容だったのだ!
それに加え、あの無農薬自然栽培「奇跡のリンゴ」の木村秋則氏や
天然醸造の酒蔵、寺田本家の寺田優(まさる)氏など
今まで私が出会ってきた注目の方々までも登場しているのだ。
とここで、寺田氏と交流を持つきっかけについて思い至った。
それは5年前、沖縄の講演会に呼ばれた時のこと。
当時発売したばかりの拙著『儲けないがいい』の
価値観と共鳴する本として、セミナー関係者から
寺田本家の先代・寺田啓佐(けいすけ)氏の
『発酵道』をプレゼントしていただいたのだ
(これが感動の本だった)。
その1、2年後、池袋のBAR
「たまにはTSUKIでも眺めましょ」(なんと週休3日!)の
オーナーであり『減速して生きる―ダウンシフターズ』の著者でもある
高坂勝氏主催のバスツアーに参加した際の行き先が、
奇遇にも寺田本家だったのだ!
“シンクロニシティ”という「意味ある偶然の一致」を指す言葉がある。
まさにこれがシンクロニシティと思ったわけだが、
今回たまたまいただいた本で全ての出会いがつながったことは、
意味ある偶然ではなく
“意味ある必然”の出会いだったのではないだろうか。
つまり、今まで様々な場でビジネス・経営観を発信してきたことが、
私の価値観に共鳴した人たちから、
価値観の似た人たち(書籍含め)を新たに紹介してもらい…と、
人との出会いが次々とつながっていったということ。
「朱に交われば赤くなる」ということわざに、
中島流として、先の“シンクロニシティ”を掛け合わせ、
“朱に交わればシンクロニシティ”と名付けたい。
価値観を明確化し発信すると、
価値観の近い人が周りに増え、そこでビジネスの機会も生まれる。
そして、その人からも影響を受けて価値観が発達し、
また別の人との出会いが生まれてゆく
(これを、以前のビジ達では
「シンクロニシティービジネス効果」と語ったのだが…)。
そして次はこの“朱に交わればシンクロニシティ”の概念を発信し、
新たな必然の出会いにつなげていきたいものだ!
そんなこともあり、次回の10月27日(木)開催
αクラブ定例セミナーは、「寺田本家」の視察セミナーとする予定。
この機会に是非、自然酒づくりを体験しよう!
詳しくは…コチラ