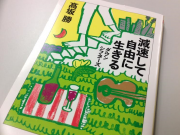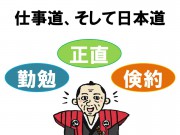05/16
2016
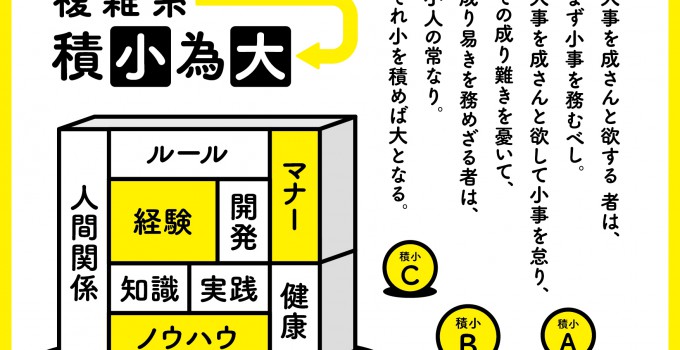
「複雑系⇒積小為大」の極意
かの有名な二宮尊徳の言葉である「積小為大」。拙著
にもこの四字熟語は登場している。これは小さな努力
の積み重ねが、やがて大きな収穫や発展に結び付くと
いった意味だ。
小事をおろそかにしていては、大事を為(な)すこと
はできないというこの教えには、私も深く共感もして
いるし、日々の生活の中でもかなり意識している。
生活面での「積小」は、日頃から食事に気を遣い、ジ
ム通いもして健康のための小さな努力を積み重ねてい
ること。そして、整理整頓を習慣にし、常に身の回り
をキレイにすることを怠らない。(まぁ~ときには、机
の上が手紙や資料でいっぱいのときはあるが…)
ビジネス面での「積小」はというと、月刊『ビジネス・
イノベーション』のCDは13年目に突入した。そこでゲス
トで登場していただいた、たくさんの経営者の方々には、
私が主催しているセミナーや、会社で請け負ったイベン
トのゲストとしても登場していただき交流が続いている。
三尺三寸箸会議の継続もそのひとつだろう。
こういった生活やビジネスでの「積小」は数えればかな
り多い。手帳の使い方やバッグのルールなども「積小」だ
ろう。これらさまざまな「積小」の複合がからみ合い…
お~これぞ“複雑系”と言えるのでは!?
そして、この“複雑系”の相乗効果を持った「積小為大」
は、より大きな結果を生み出していくのでは、と私は思う
のだ。
例えば、大里綜合管理の事業展開もまさにそうだ。多数の
地域貢献活動は直接的な収益にはならない「積小」だが、
積み重ねることで、この会社に対する大きな信頼を獲得す
ることとなる。その信頼はひいては大里のビジネスである
不動産事業にも大きな利益をもたらしている。
小さなことを積み重ねていけば、チャンスも多くやってくる。
そしてそれが増えることで可能性も大きくなってくるのだ。
今後も、いろんな「積小」を重ねていくことが私たちのビジ
ネスの中で重要であることは間違いないだろう。まさに“複雑系”
の「積小為大」である。
こうして考えると、私の仕事は本当に今まで出会ってきた、たく
さんの人との関係によってつくられているってこと。人は“複雑系”
の中で生きていることを実感。
「平凡の積み重ねこそが非凡を招く」と鍵山相談役も言っていた
ことだし…。そのためにもこれからも毎日コツコツ、小さな努力を
積み重ねていかなければ。