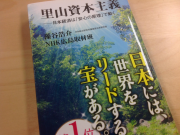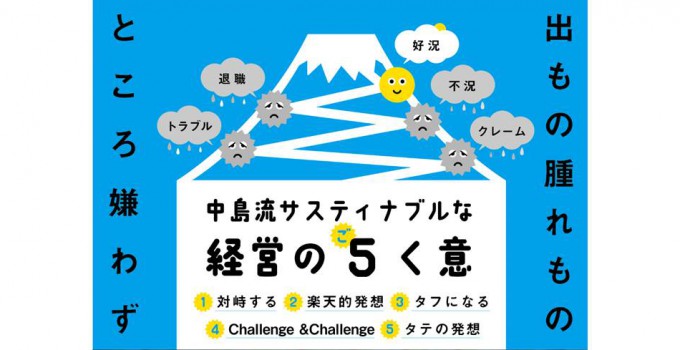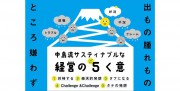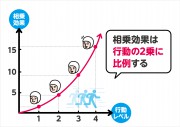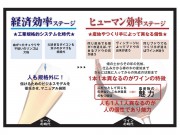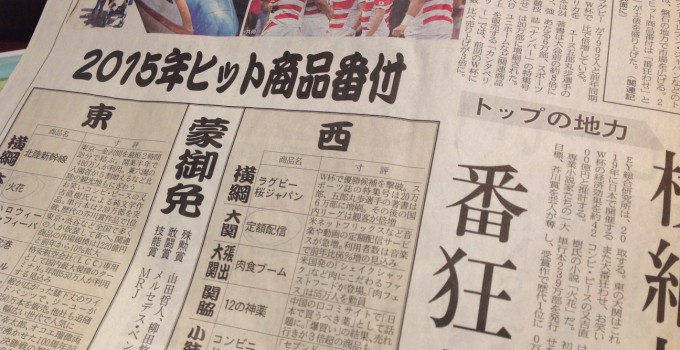02/29
2016

里山を活かした“地消地産”
“地産地消”という言葉をご存知の方は多いだろう。
地元で生産したものを地元で消費するということだ。
ところが、今回のタイトルは“地消地産”。
地産地消と似ているが、
“地元で消費するものは、地元で生産したものにしよう”
という考え方のことだ。
先日、私が主宰しているアルファクラブの定例セミナーで、
あの“里山資本主義”の藻谷浩介氏を講師としてお招きした。
藻谷氏には“里山資本主義”を中心にお話してもらったのだが、
そこで強調していたのが“地消地産”。
この考え方が、日本の課題となっている
地方の過疎化の解決に貢献するというのだ。
労働人口というのは15~65歳の働き手のことを指す。
全都道府県において、いまも人口増の東京都であっても、
労働人口は減っているそうだ。
とすれば、他の地域の労働人口が
減少の一途を辿っているのは想像に容易い。
そんななか、労働人口を増やすキーワードが
地消地産なのである!
私の故郷である北海道十勝は農業が盛んで、
計算上の食料自給率は1000%を優に超す。
ところが実際に地元のものを食べている割合はというと、
40~60%ほど程度だという。
日本の他の地域とあまり変わらず、
自分の地域以外でつくったものを多く食べている。
その理由はコンビニやファストフード店、
大手スーパーなどのメジャーブランドから
購入したものが多数だから。
そして、こういった大手ブランドは中央に本社があるため、
地元で買い物をしても
その多くは都心に吸い取られてしまうということ。
もし“地消地産”を徹底することができれば、
この悪循環を断ち切ることができる。
例えば、道の駅の多くは一見観光客向けのように思われるが、
もっと地元の人が利用したくなる品揃えにするだけでも
かなり“地消地産”が進むはず。
私が昨年から実現に乗り出した
十勝ワインヴァレー構想も、“地消地産”の1つだと言えよう。
昨年は550本のぶどうの苗を植え、
さらに今年は4500本の苗を植える予定だ。
ここにご協力をお願いしているのも、
もちろん地元の農家の方々。
ゆくゆくは何万本もの苗が成長し、
地元で生産したぶどうを地元でワインに加工…。
そして地元の方々に飲んでいただくのである。
(もちろん、外貨を稼ぐために外にも販売はするが…)
石油や車、衣類など、
どうしても地元で生産できないものを除き、
できるだけ地消地産を徹底することが
結果として労働人口の減少を食い止めるということなのだ。
いずれ引っ越したいと思う若者や、
結婚してUターンし、
子どもを地元で育てる夫婦が増えるかもしれない。
町が活性化するきっかけが、
この地消地産に秘められているのだ。