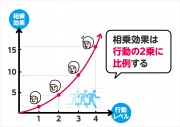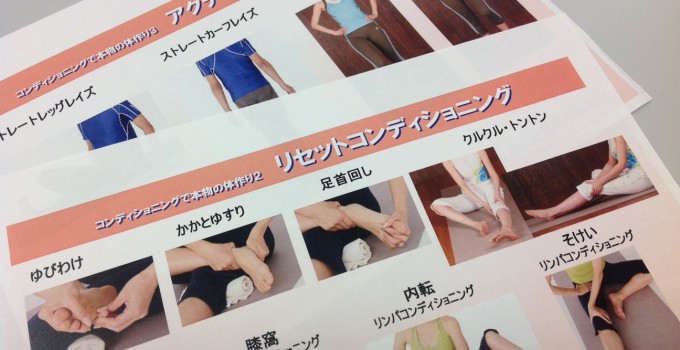07/06
2015

藻谷浩介流「里山資本主義」
「この間、大根50本貰ったんだよ、
だからお返しにお米10キロあげようと思うんだ」
こんなやりとりの話をしてくれたのは、
ビジ達でも紹介した『里山資本主義』の著者・藻谷浩介氏。
先日、そんな藻谷氏と
「里山資本主義」をテーマにお話をする機会があった。
そこで出てきたのが冒頭の物々交換の話だ
(私も子どもの頃にはよくあった光景だ)。
田舎では里山の恵みを使った物々交換はもちろん、
物以外の交換も盛んに行われている。
例えば、子どもの多い家庭に
ご近所さんが衣類やおもちゃを持って行き、
子どもの元気な成長をお返しにする。
また、風雨で壊れた家があれば、
みんなで集まって修復し、
家主がお礼にお餅を振舞う、などだ。
このように、里山や地域の人々が寄り添う田舎において、
対価をお金ではなく
物や手間で返すことは日常的に行われている。
藻谷氏は、このお金を必要としない里山生活に、
お金を稼げるビジネスを加え、
バランスよく生活していくという
「里山資本主義」を提唱している。
すなわち、これまでの資本主義に里山的生活を加えた
新たな暮らしの提案をしてくれているのだ。
藻谷氏が提案するビジネスは、
里山の資源を活用した
地域循環型のビジネス(里山ビジネス)だという。
過去の事例には、
それまで産業廃棄物として処理していた木屑を加工し、
燃料ペレットとして地域の施設に販売したり、
食べきれない農作物を地域の施設で活用したり、などがある。
このように、里山を活用したビジネスの提案は
里山の保全につながり、
それによって川や海などからも
良質な資源を手に入れることができるのだ。
このところの日本は、高度成長期の頃から、
お金だけで解決しようとする流れになってしまった
(私はこれを強欲資本主義と呼んでいるが…)。
しかし、その流れはいま全国的に出現している
「里山ビジネス」の登場で変わりつつある。
里山ビジネスは、
現代が抱える問題(雇用・少子高齢化など)を
解決に向かわせるだけでなく、
その地域のコミュニケーションを深めることにもつながる。
このようなサスティナブルな
価値観が見直され始めているのだ。
これまで私はビジ達や講演を通して
「里山ビジネス」の必要性について
さまざま角度から発信してきたが、
そのベースの考え方は藻谷氏の話と
オーバーラップする部分が多い。
やはりビジネスにおける価値観は
少しずつではあるが変わりつつあるということだ。
このように里山を活用したビジネスや
新たな街づくりをどう実践していくかが、
これからのビジネスに求められていることなのだろう。
──────────────────────
『里山資本主義』の著者・藻谷浩介氏が登場!
里山を活用したビジネスの未来を探る!
7/12・19放送の『BUSINESS LAB.』をお聴き逃しなく!
InterFM『BUSINESS LAB.』
東京76.1MHz・横浜76.5MHz
毎週日曜 朝6時から好評放送中!
──────────────────────