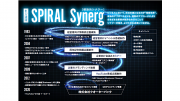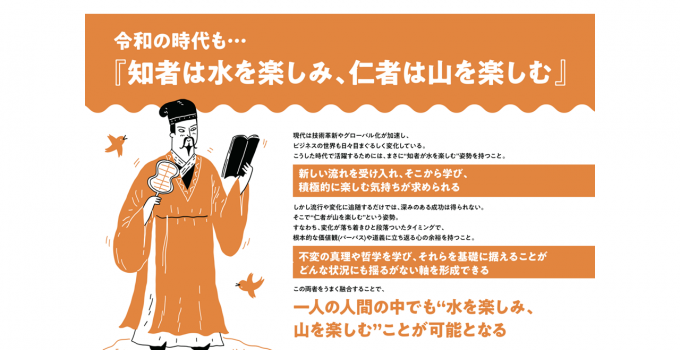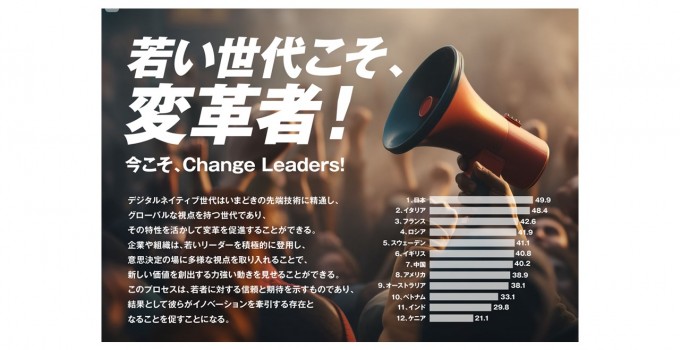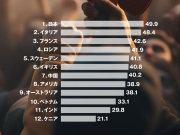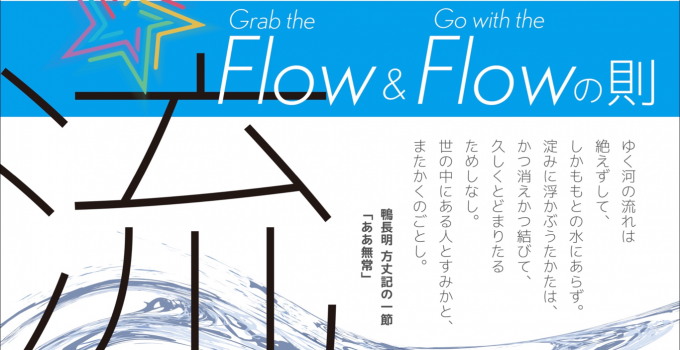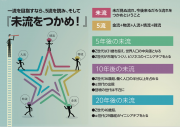11/25
2024
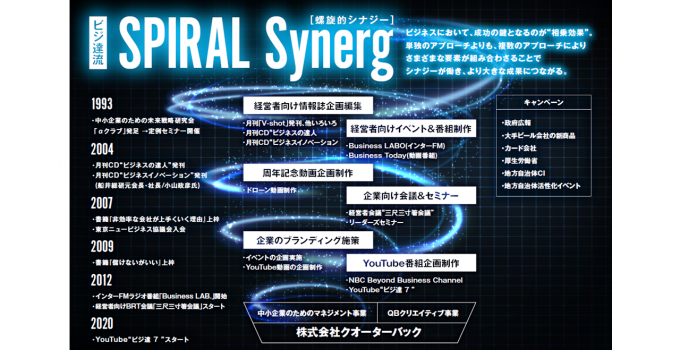
令和の時代も成功のカギは SPIRAL Synergy螺旋的シナジー
私たちのビジネスにおいて、より大きな“相乗効果”を得るには
どうすればいいのだろう?
→異なる部門からのメンバーを集め、
多様な視点や専門知識をもとにプロジェクトを進める。
→他の企業や団体と提携し、それぞれの強みを活かすことで
リソースを共有しながら進める
ふむふむ…
今回は、私が実体験した弊社“クオーターバック”における
相乗効果、SPIRAL Synergy[螺旋的シナジー]を紹介したい。
長期に渡る効果的な相乗効果である。
【1993年、中小企業の経営者向け会を発足!】
私は会社を創業して、10年ほど経ってから“経営者の会”をつくり、
経営者のためのセミナーを定期的に開催することに。
毎回、著名な経営者をお迎えし、
講演もしてもらうが対談セッションもさせてもらった。
そしてそれら多くの経営者には、全国の経営者向けの
月刊CDにも登場してもらったのだ。
1993/中小企業のための未来戦略研究会「αクラブ」発足
→定例セミナー開催
2004/月刊CD“ビジネスの達人”発刊
2004/月刊CD“ビジネスイノベーション”発刊
(船井総研元会長・社長/小山政彦氏)
2007/書籍『非効率な会社が上手くいく理由』上梓
2009/書籍『儲けないがいい』上梓
◆お付き合いのある注目の経営者を取材させてもらい、
その経営の流儀を中島流に解釈させてもらい
書籍も出版させてもらった。
◆ビジネスをテーマに民放のラジオ番組もプロデュースし、
そのキャスターも務めさせてもらった。
【本来の“クリエイティブ事業”に相乗効果が!】
私が創業した“株式会社クオーターバック”の本来は
広告やブランディングに関わるクリエイティブ事業。
だが私が経営者向けのコンサルティングにも興味が
あったことにより、これら事業施策になっていたということ。
(すでにシナジーを期待しての展開だったかも…?!)
そしてこれら経営者向け施策に登場してもらった
多くの著名人や経営者とのお付き合いが、
競合他社にはなかなか実現することのできない
“クリエイティブ事業”の企画提案につながったということ。
それら企画は、多くのコンペティションでも選ばれ、
そして好評を得ていたのだ。
まさにここに相乗効果が発揮されていた。
◆経営者向け情報誌企画編集
月刊「V-shot」発刊、他いろいろ
◆周年記念動画企画制作
◆企業のブランディング施策
→イベントの企画実施
→YouTube動画の企画制作
◆さまざまなキャンペーン施策
政府広報キャンペーン
大手ビール会社の新商品キャンペーン
カード会社キャンペーン
厚生労働省キャンペーン
地方自治体活性化イベント
↓ ↓ ↓
ということで、私たちが展開する“クリエイティブ事業”は、
他の業界に比べて、そのほとんどが企業規模も小さく
そして競合も多い厳しい業界。
その中にあって成功の鍵となるのが“相乗効果”。
単独のアプローチよりも、複数のアプローチにより
さまざまな要素が組み合わさることで
シナジーが働き、より大きな成果につながるということ。
これは私たち業界だけではなく、
すべてのビジネスにも言えることだろう。
「“相乗効果”を制する者は、ビジネスを制す!」
ということのようだ。
ちなみに、なぜ“SPIRAL Synergy螺旋的シナジー”
と呼ぶのかは、また次の機会に!