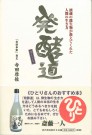08/19
2013
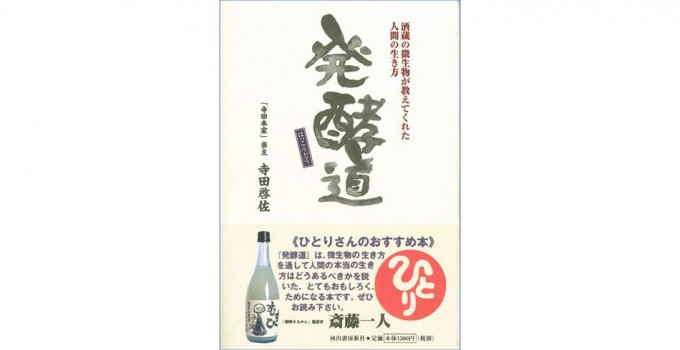
腐敗から発酵へ
時々足を運ぶ、
池袋のOrganic Bar「たまにはTSUKIでも眺めましょ」。
そこでは決まって発芽玄米酒「むすひ」をよく飲む。
少し酸味があるが、そのコクというか
クセというかがよくなってくるのだ。
そんな「むすひ」は千葉県にある
自然酒蔵元「寺田本家」でつくられている。
その蔵元の当主である寺田啓佐(てらだけいすけ)氏は
6~7年前に『発酵道』という本を出版。
私もその本を読み、以前このビジ達でもご紹介させていただいたのだが、
ここ最近その本の内容が、
まさに今の時代にあったものだと感じ、
つい最近になって再度手に取ったのだ。
その本の内容というのが、
自然酒造という形式で酒づくりをしている寺田本家の話。
酒造りの過程で、無理に菌を加えるのではなく、
乳酸菌や酵母菌などそれぞれの菌や微生物たちが、
まるで自分の役割を果たしバトンタッチをするように、
思う存分働いていることで美味しい酒が出来る、というもの。
これが自然の中での“発酵”。
多種多様な微生物たちが役割を持って
登場してこないと美味しい酒づくりは出来ない。
そして、やはり自然界は競争の原理ではなく、
協調の原理のほうが強く働いているということ。
つまり、それぞれの役割を全うすることで、
生態系全体の安定を保ち、循環しているのだ。
さて、私たちの世の中はどうだろうか。
自分本位な人であふれ、人より多く、人よりいいものを、
都合のよいタイミングで求める人であふれかえっているように感じる。
他人を蹴落とし、自分を優先させるというまるで「イス取りゲーム社会」のよう。
私たちはここ100~200年の中で、利潤を追い求め過ぎた結果、
社会を“腐敗”させてしまったのだ。
それではそこから脱却し、
争わなくても活かされる社会をつくっていくにはどうすべきだろうか。
そこで注目したいキーワードが “発酵”。
それぞれが誰かのためになることを一生懸命行う。
自分の役割を考え、真摯に実行する。
すると、寺田本家の酒の製造過程のように、
それらが連携し自然にバランスのよい社会がカタチづくられていく。
そこにはムリもムダも少なく、サスティナブルな社会へ。
この時、腐敗しつつある社会は発酵する社会になるのだ。
発酵道はすなわち仕事道に通ずる。
これからは“発酵”というキーワードに注目!