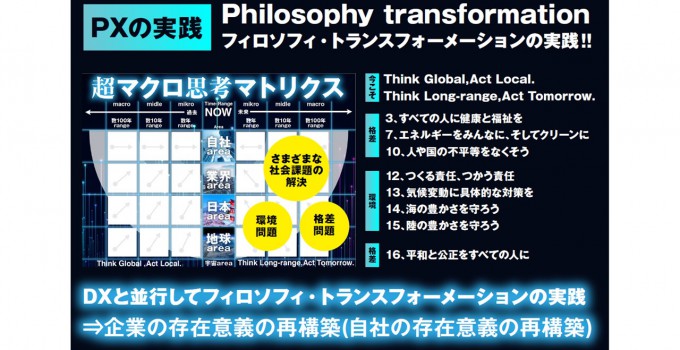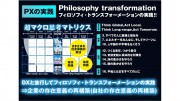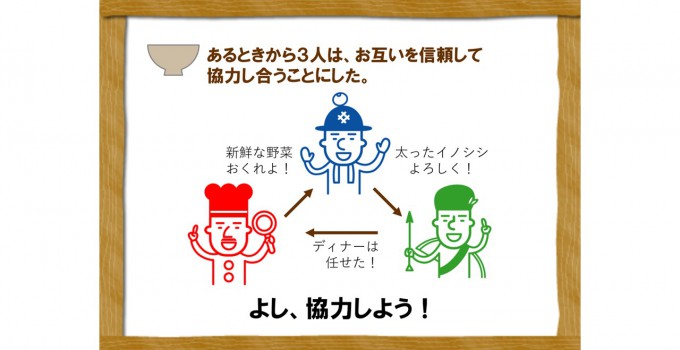03/14
2022

ロボット“ベラちゃん”によるRPAの現場!?
私の隣の席にベラちゃんは現れた。
その猫表情のロボットは“お待たせいたしました、
注文の料理です”といい、
お客さまも慣れているかのように、
料理をロボットの背中側より取り出している。
そして取り出し終わるとお客さまが終了らしきボタンを押している。
(押さなくても、帰っては行くようだが…)
すると踵を返して戻る時には“お食事を楽しんでください”だって!
ベラちゃんの表情は状況に応じて変わる仕掛けだ。
子どもたちにも人気だとよくわかる
このお店は100席ほどあるお店なのだが、
この“ベラちゃん”が結構頻繁に活躍している。
もちろん私は取材も兼ねてここ来ているわけだから
写真も撮るが動画も撮ろうと用意万端。
さて私のランチもそろそろロボットが運んでくる頃かなぁと
スマホを準備して待っていたわけだが…
すると…少し大柄のおネエさんが私のテーブルの横に立ち、
“お待ちどうさま、ご注文の日替わりランチです”だって。
私も正直に“え〜ロボットじゃないの⁈ ”というと。
そのおネエさんは“ロボットが出払ってまして、私が…”というのだ。
“え〜私だけ何で⁈ ”とは言えなかったが、心の中で叫んでいた。
ということで、おネエさんの許可を得て動き回るベラちゃんを
撮らせてもらうことに。
この“ベラちゃん”とは、すかいらーくグループのファミレスにいる
ロボットのことだ。
今やパソコンやスマホのアプリによりDX化がどんどん進んでいる。
そして、ロボットにAIをプラスした
RPA (Robotic Process Automationの略)化が
身近なところに押し寄せてきていることを体験しに、
調布にある“ガスト”へ行ってきた。
実はこの“ベラちゃん”は感染症対策にも効果があり、
人件費高騰の余波もあり大活躍だ。
配膳・下げ膳などの単純作業を任せることで、
オーダー促進、メニューの説明、会計などの接客業務に
スタッフが集中できると聞いた。
実際に、知人が“ガスト”で働いているので聞いてみると、
この“ベラちゃん”のおかげでかなりラクになっていると。
ロボット供給会社の説明では、
1ヶ月の人件費は、最低賃金930円で
12時間労働×30日×930円=334,800円。
“ベラちゃん”のコストは月額利用料が44,300円の
5年リース(保守サポート費込み)なので
なんと毎月290,500円もお得という計算をしている。
(少し乱暴な計算過ぎるが・・・)
人間1人の役割までもしてくれるかどうかはともかく
働いている人にとっては助けになっていることは確かなようだ。
さて、これからビジネスでも生活でも、RPA化がどんどん
私たちの周りにやってくると予測できる。
会計の仕事や弁護士事務所の過去の判例を探すことや・・・。
私たちの広告業界でも、これまでの似た多くの事例から
案を提案することも訳ないことかも知れないのだ・・・。
(プロの居場所がなくなる可能性も)
そうこうするうちに・・・、
その貴方の仕事もロボットに奪われるかもしれない?!