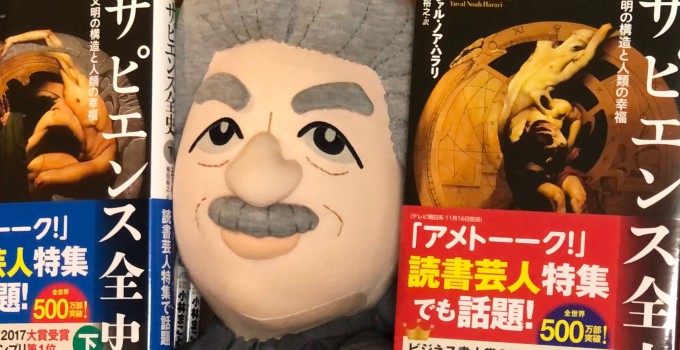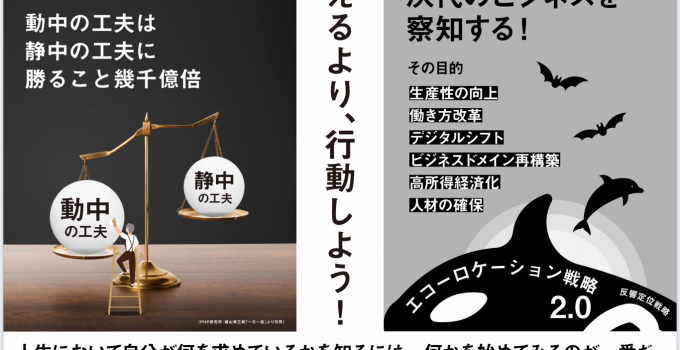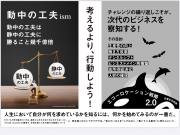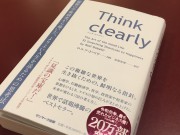08/09
2021

“オリンピズム”を理解しよう!
オリンピックに関して、
“なぜ、日本政府は東京五輪を中止しないのか?”
“本来の意味を果たさないオリンピックは中止すべき”
“無観客は開催の意味がない”
このような発信を度々メディアで耳にした。
それもかなり立場のある人たちも発進していたのだ。
この方々は、果たしてクーベルタン男爵が
オリンピックを再開した時に定めた
オリンピックの普遍的社会哲学を理解しているのか・・・?
と私は言いたい。
オリンピックは日本の都合だけで開催されているものではない。
この世界的なパンデミックの中にあっても敢えて
オリンピックをする意味があると私は思っている。
それほどオリンピックは世界にとって重要で尊いものだと改めて伝えたい。
クーベルタン男爵は、1894年にオリンピックの構想を提案。
1896年第1回近代オリンピックをアテネで開催。
クーベルタンは“オリンピズム”とは、
「肉体と意志と知性の資質を高めて融合させた
均衡の取れた総体としての人間を目指すものである。
オリンピズムの目標はスポーツを人間の
調和の取れた発達に役立てることにあり、
その目的は、人間の尊厳保持に重きを置く
平和な社会を推進することにある」としている。
(うんうん、さすがクーベルタンである)
私は、オリンピックにおいて
200を超える国と地域の人々が一同に会し、
スポーツを通じて交流を深め、関係者や
多くの観戦者も含めた人々が
ひとつの丸い地球で皆が暮らしている意識を
持つことが重要だと思っている。
私は柔道の経験があるので、柔道を好んで観ていたが、
日本のメダルラッシュよりも、ジョージアの人たちの強さや
ヨーロッパの選手、アメリカ大陸の選手達も
かなり力をつけてきていると感じ、
柔道を通して、地球規模での世界の今を
感じたわけだ。
これは、オリンピックだからこそできること。
1964年の第18回の東京オリンピックでは、参加国は
93カ国で、参加者は、5~6千人だった。
今回は205の国と地域から1万2千人を超える人たちが参加
しているので、倍以上になった計算だ。
オリンピックでは、自国を応援しながらも、
地球にはいろんな人がいて
それぞれの存在を尊重していかねばならないと気づく。
78億人がスポーツイベントを通して、興味と感動を創り出し、
まさにダイバーシティを実感できる
かけがえのない機会だと言いたい。
過去には戦争で開催されないことも、国と国の利益が反して
参加を見送ることもあったが、開催することにより
相手を尊重することを覚えていく。
決して選手のためだけのオリンピックではないわけだ。
日本にとって、当然、経済的には有観客の方がいいのだが、
開催することに意味がある。
今回、多くの国と地域の参加により、
クーベルタン男爵の言う“オリンピズム”は
きっちり活かされていると感じた。
やっぱり、オリンピックは地球規模で
“参加してくれること”に意味があるわけだ。