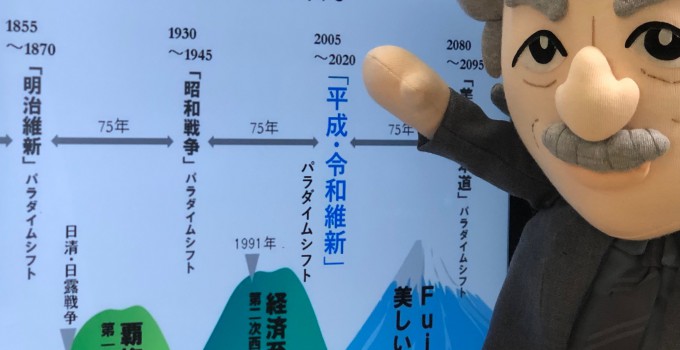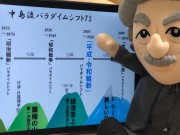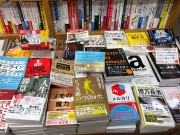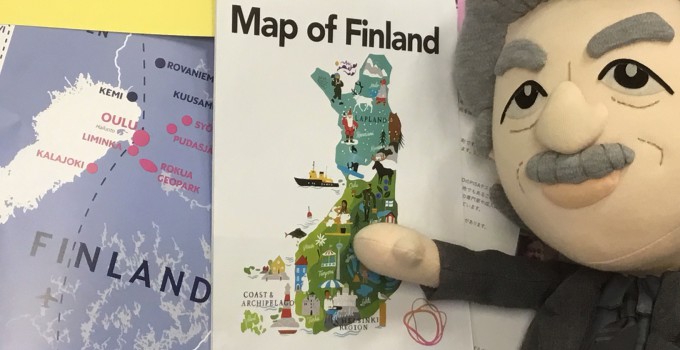05/27
2019
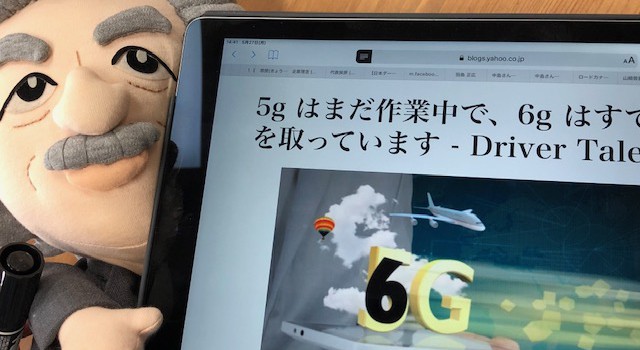
Beyond 5Gへ
「5gはまだ作業中で、6gはすでに形状を取ってます」
さて、何と読みました?
「ごグラム」「ろくグラム」と読んだ方はきっとちんぷんかんぷん。
「ファイブジー」「シックスジー」と読んだ方には、
今回の話が読めているかも。
大容量通信“5g(G)”の時代はすでに見えてきている…と、
このビジ達では繰り返しコラムにしてきた。
(先日検索していると、表記が「G」ではなく
「g」で出てきたのだ)
しかし、フィンランドのオウル大学では、
すでに2030年の実現を目指し、
6gの超超大容量通信に仕掛かっているという。
これは5gで目指した大容量通信をより進化させ、
高いデータレート(速度)と容量を実現させるというもの。
まだ、実現されていない5gですら
4K,8Kの高精細画像を遅延なく、
長距離通信もできるわけで、
これまでなんとももどかしかった
テレビ会議もスムーズになるという。
地球の裏側から内視鏡手術をすることも可能になる。
家電のIOT化、働き方改革もますます進むだろう。
これまで「農家は畑を離れられないもの」
とされていた農業でも、遠隔でロボットを操作して
作業をすることが可能になる。
そして、5gとともに、働き方・インフラに関する
考え方が根本的に変わる時がやって来ているのだ。
余談だけれど、この頃関税関係で
軋轢が絶えないアメリカと中国の関係にも、
この5gが関係しているとか。
中国(ファーウェイ)が5gでは一歩先を行きつつあり、
アメリカは巻き返しを図りたい気持ちがあって、
今回の関税はいわば代理戦争だそうな…。
大国同士が争うほど、今やIT覇権を握るものが
ビジネスの覇権を握るとも考えられるだろう。
もちろん、私たちにとってもそれは他人事ではない。
5g時代が来るのはもはや当然。
その先の6g時代、私たちのビジネスはどう進化するべきか?
何ができて、どんなサービスが求められるのか?
まずは、5g時代が来て、さまざまな新しいビジネスや
サービスが出てきて、新たな働き方も見えてくると、
次なる6g時代も予測できるようになるのでは…
とはいえ、いまから2030年の6g時代を意識して、
5g時代を迎えることは意味のあることに違いない。
やっぱり表記は「5g」「6g」ではなく
「5G」「6G」として欲しい。