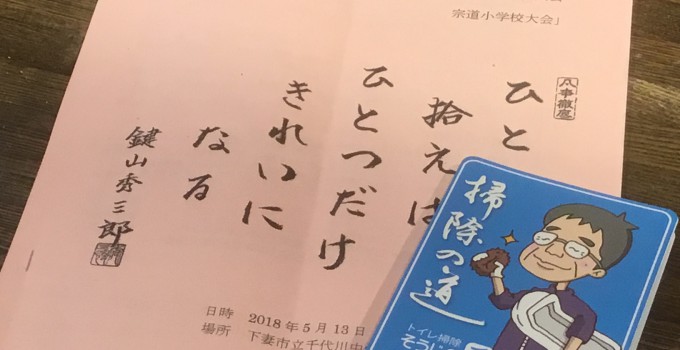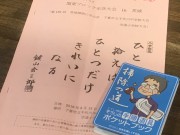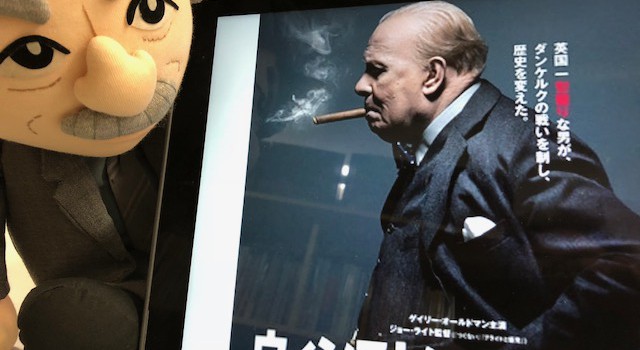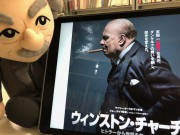08/20
2018

ブランディングへ「ハレの日」活用
先日のビジ達でもご紹介した、
浜松市で建材販売会社を60年展開する「株式会社原川」。
60年を振り返り、100年に向けた運営姿勢を発信する
オープニングビデオを製作させていただいたのだが…。
当日このイベントに参加し、
社員の人達の反応を見て感じたことがあった。
地域や業界を代表する取引先の人たちが
自社の周年イベントに全国から集まっている光景を見る。
(250人近くの人たちが集まってくれていた)
それだけでも、自社が多くの人に関わり、
注目される会社だということに
改めて社員の人たちが気付くことになる。
これは、社員の人たちの帰属意識の高揚にもつながるだろう。
そう、重要なのは自社への誇りであり、帰属意識なのである。
いままさに、東京上野で55年間お店を展開する
会社のビデオを製作しているわけだが…。
私はここでも、社員の人たち全員を
ビデオに登場させることにした。
それは…
自社への帰属意識とブランディングに対する意識を
社員一人ひとりに持ってもらうためだ。
どうあればこれからも自社は存続するのか、
どんなサービスを展開すれば、
多くの人たちが選んでくれるのか、
どんな関係を築けば、大切に取引してくれるのか…。
そう、記念の節目(ハレの日)を
全社員が会社の未来について考える
きっかけにしたいと考えたのだ。
ブランディングというのは
つい外に向けるものと考えがち。
ところが、社員を巻き込み、共感や信頼などを育てていくことで
社員自身もそのブランドを
意識した行動をとることにつながり、
ひいてはその価値を高めていくのである。
時代の流れやトレンドによって、
生活者のニーズや社会の情勢は変わっていく。
その中で、当然企業のブランドは新陳代謝を余儀なくされるわけで、
そこで働く人たちが、自社ブランドを理解しながら
時代にあった価値を追求していこう心構えは
これからの時代、必ずや必要になってくるということ。
そして周年イベントといった「ハレの日」は
そのきっかけづくりに最適ではないか。
ブランドの新陳代謝のためにも、
ハレの日をブランディングに活用していこう!