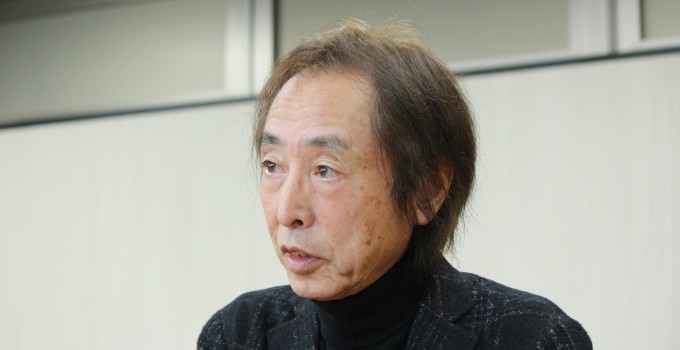04/02
2018
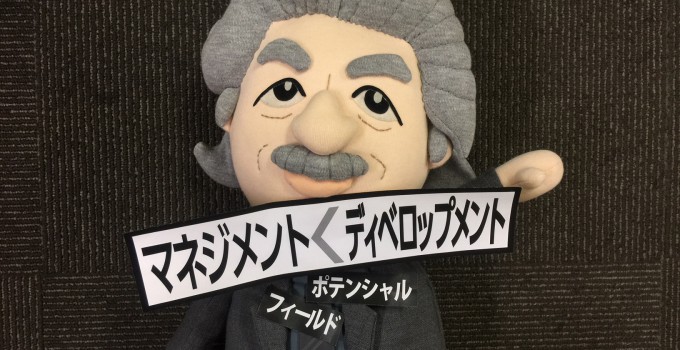
混沌の時代は“マネジメント<ディベロップメント”
新たなビジネスモデルが次々と登場している現代。
こんな時代に、企業力や生産性を上げるためには
どうしたらよいのだろうか?
先日、先輩コンサルタントが、ビジネスにおいて
生産性を上げるための2つの方法を話してくれた。
1つ目は、スタッフの“ポテンシャル”を上げること。
セミナーを受けて視野を広げたり、人材開発をして、
新しい技術やノウハウを身に付けさせたり…。
つまり、会社のスタッフ・組織の能力を底上げしていくということ。
2つ目は、“フィールド”の拡大。
自分たちの取り扱う領域を広げ、
生産性・売り上げを高めていくということ。
より多くのお客さまを囲い込み、
広い範囲で商品やサービスを展開することがねらいだ。
まさにこの2つを意識して経営していくことは、
今の時代必須といえるだろう。
パラダイムシフトの過渡期といわれているこの時代。
ビジネスにおいても、次なるステージを目指すのは必然である。
さて、これらを進める上で経営に必要な概念、
マネジメント(管理)とディベロップメント(開発)。
これらにおいても、過渡期のいまだからこその考え方を提案したい。
安定的なパラダイムが確立されている環境では、
ディベロップメントよりもマネジメントを優先することが大切。
なぜなら、本来のテリトリーで効率よくやっていくことが
生産性向上につながったからだ。
ところが、過渡期になると世の中の景色はどんどん変化していく。
時代に取り残されないためには、さまざまなチャレンジが必要となり
ディベロップメントに重きを置かなければならないのだ。
企業力・生産性を上げ、競合に負けず生き残るためにも、
ポテンシャルの向上とフィールドの拡大は重要。
そして、意識はディベロップメントへ。
人も組織も管理するより、レベルアップさせ
次のステージへ成長を促そう。
経営者のチャレンジは、終わらないのだ!