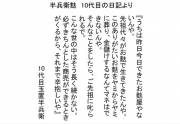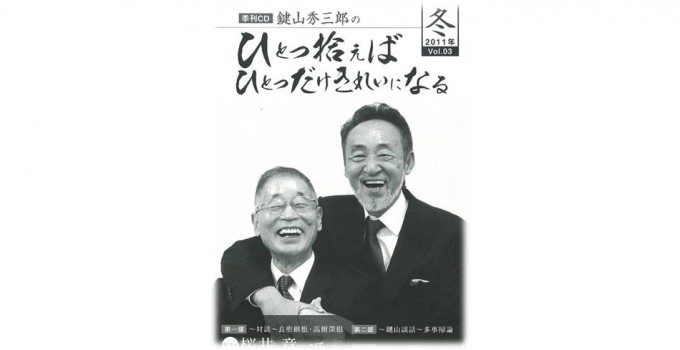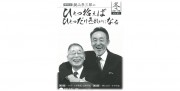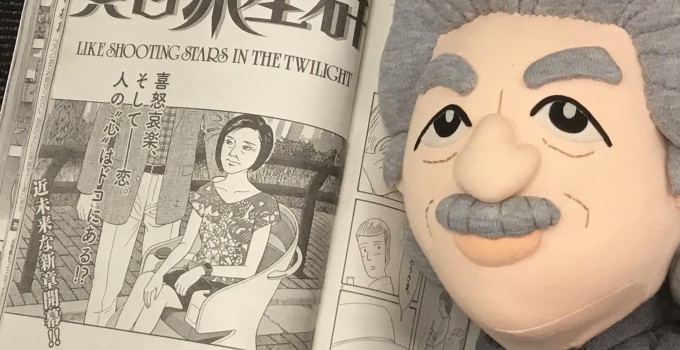12/18
2017

「先義後利が塾」発進!
今、北海道の十勝芽室町で展開している
“Memuroワインヴァレー構想”。
私がその根本に据えているテーマは、
「孫子の代に何を残せるか」だ。
そこで、せっかく毎月芽室町に行っているなら
その間になにかできることがあるのでは…?
と考えたのだ。
そこで思いついたのが、「先義後利が塾」!
芽室の若者たちが世の中を理解し、
地球規模で物事をみてチャレンジできるように
寺子屋的塾を開催し、発信することにしたのだ。
なぜ、「先義後利が塾」なのか。
拙著『儲けないがいい』のテーマでもある「先義後利」。
“義を優先し、利を後回しにせよ”という意味。
やっぱり、地球規模でみてもこの日本的価値観は
忘れてはならないってこと。
ところで、ビジ達で何度もお話している
先義後利だが、私がこの言葉と出会ったのは
いつのことだったか…。
今から15年ほど前、
創業300年を超える京都の老舗お麸専門店、
半兵衛麸の11代目当主に取材するという機会があった。
この半兵衛麸の家訓が、“先義後利”だった。
半兵衛麸の10代目の日記によると、
戦後間もない頃は麸の材料を確保するのも
難しい状態が続いたが、
決して正規のルート以外から仕入れることはなかったという。
『うちは昨日今日でできたお麸屋やないんや。
先祖代々がお麸で生きてきたんや。
このありがたいお麸をヤミからヤミに葬り、
金儲けするなんてマネはできないんや。
そんなことをしたら、ご先祖様に叱られるで。』
という日記。
結果的に、半兵衛麸は10年以上暖簾をおろすことになったのだ。
店舗を再開させるまでは
とにかく長い時間だっただろう。
しかし、暖簾をおろす前から社会性を重んじ、
通すべき義を守ったということ。
そして店を再開させるには苦労は多かったが、
以前のお客さまが応援してくれたのだ。
いまや京都では、半兵衛麸のお麸尽くしのランチは大人気という。
徹底するには勇気がいるが、常に意識したい言葉が“先義後利”。
ビジ達でもお話している「パラダイムシフト75」の通り、
時代は過渡期に差し掛かっている。
先義後利の意識を徹底していかないと、
私たちのビジネスも乱れて、社会も秩序を失ってしまうのだ。
芽室の地でかまえた、「先義後利が塾」!
北海道の地で、たくさんの若者へ
先義後利の重要性を発信していこう!