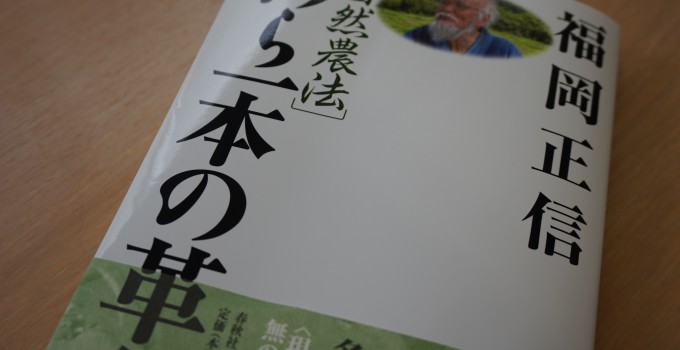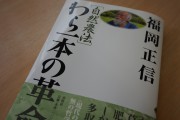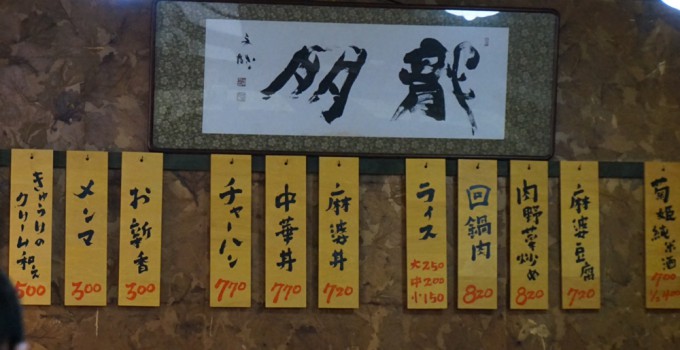04/06
2015

明倫館から学ぶ風土づくり
風土は、人の成長に大きな影響を与えるものだ。
先日、山口県萩市にある明倫小学校を訪問させていただいた。
ここは、元々長州藩の藩校“明倫館”のあった場所で、
吉田松陰も明倫館で教鞭を執ったと聞いている。
その明倫小学校で、1年生と5年生が吉田松陰の言葉を
朗唱する様子を見学させていただいたのだ。
訪問してまず目に入ってきたのは、下駄箱に履物が
一糸乱れずきれいに並べられていること。
廊下の展示物も、床もゴミなくきれいに保たれている。
こうした明倫小学校の様子を見て、
明倫館の伝統であり風土が
しっかり代々受け継がれていることを感じた。
こうした環境で身に付けた常識や精神は、
大人になっても引き継がれていくだろう。
すなわち、社会に適応するのはもちろん、
活躍する人間をつくることに繋がるだろう。
やっぱり、子どもの頃の環境こそが、
人をつくるのだ。
私の事例だが、小学生の頃の校長先生と担任の先生が、
武道に精通しており、
教育にも積極的に武道を取り入れていたことから、
私も先生方に倣って柔道を始めた。
それからは、私の成長のそばには常に柔道があり、
(部活で柔道ばかりやっていた訳ではないが…)
そのため私の中には常に武道の意識がある。
体が小さい方だったこともあり、
常に自分より大きい人との対戦を意識して稽古していた。
すなわち、“柔よく剛を制す”をテーマに
していたということだ。
これらの武道の経験で学んだのは、
人との間合いと日々の鍛錬の大切さ。
私のビジネス観にも“柔よく剛を制す”の
精神と、“積小為大”の考え方はしっかり
活きている。
この様に、若いときの環境が、
その後に大きく影響するのは間違いないだろう。
だから私は、会社の風土づくりは、
かなり意識してきたといえる。
弊社もお陰様で30数年の社歴があるが、
明倫館から明倫小学校へ受け継がれたように、
目に見えないものではあるけれども、
文化や風土は活きているのだ。
創業からのスピリットや考え方、
業界に対する価値観、
そして、クリエイティブの世界で
“存在意義”をどうつくっていくのかという
弊社ならではの“風土”を常に意識してきたことが、
今に繋がっているのだろう。
改めて目先の戦略や戦術よりも
“ロングレンジで活きてくる風土”の
大切さを再認識することができた。