02/23
2015

“経営マトリックス”が推進力
「マトリックス」という言葉の由来を
ご存知だろうか。
実は、Mater(母)+ixという組み合わせで
「子宮」を意味するラテン語に由来しており、
そこから何かを生み出すという意味を持つそうだ。
何かを生み出す…。
会社の経営推進において、何が一番機能しているのか?
それはもちろん人であることは間違いない。
しかし、実のところ会議体こそがマトリックスの根本にあるのだ。
一時、「すごい会議」という会議が新聞などで、
大きく取り上げられ注目されていた。
仕事として取材もさせていただいた記憶が…。
やっぱり、会議体こそが会社の経営推進の原動力なのでは…。
そして、組織内にある様々な部署の連携が行われているのも会議体なのだ。
注目すべき点は、5W1Hの徹底。
誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どのように
進めていくのかという最低限度のことをきっちり決定すること。
それが、一人ひとりに責任感をもたらすのだ。
その役割があってこそ、会議が経営の推進力を生む
きっかけになる。
こうした取り組みは弊社でも行っている。
役員が集まって行う会議からマネージャークラスが集まる会議、
テーマを持って担当者が集まる会議、社員全員が集う会議など。
部署やチームなどを超えて連携をとることが、
会社の経営に大きな影響を与える。
そして、一人ひとりの意識を高めてくれるのも会議体なのだ。
まさに、ヒエラルキーの組織(図)より
会議体こそが経営のマトリックスということ。
1つの事例をご紹介しよう。
私が主宰となり、モデレーター役を務めている
“三尺三寸箸会議”。
この会議は、様々な経営者が定期的に集まって、
会社の経営手法についてディスカッションし、
そこで得たものを自社へ持ち帰り、
経営の推進に役立てている。
会議体は、その時代、時期への対応や
現状の問題点の改善など
様々な答えを導きだしてくれる。
すなわち、何かを生み出すマトリックス
となってくれるのだ。
会議体をうまく活かすことが、
過渡期を迎えるこれからの時代の
会社経営には、非常に重要ということ。
経営マトリックスはまさに“会議”なのだ。
会議を制する者は、時代の経営をも制す!






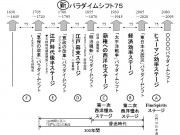


-680x350.jpg)

![ara] (2)](https://bt.q-b.co.jp/wp-content/uploads/2015/02/ara-2-101x135.jpg)

-180x135.jpg)





















