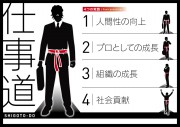12/15
2014

ブドウの木は“経済効率”では育たない!
「農業は続けることに意味がある。その土地を絶えず耕して、
そこから恵みを受けながら、人も植物も生き続ける。
それが農業であり、人間の暮らしである。
ワイナリーを中心に地域の人が集い、遠方から人が訪ねて来、
そこでつくられたワインや野菜や果物を媒介にして
人間の輪ができあがる。それが来訪者を癒し、
地域の人々を力づけ、双方の生活の質を高めていくことにつながるだろう。
ワイナリーじたいはとりたてて大きな利益を生むものではなくても、
そうした、農業生産を基盤として地域の永続的な発展と活性化を
促すひとつの有効な装置として機能するとすれば、
これほど大きな価値を実現できるものは他に類がないと思う」
(※玉村豊男著「里山ビジネス」本文より一部引用)
(すばらしい! 大変共感させられる話だ)。
これは、長野県の東御(とうみ)市でワイナリーとレストランを経営する
玉村豊男さんが、果実酒製造免許を申請するときに税務署に提出した、
ワイナリーの設立趣意書の一部分。
よいワインづくりには時間とお金がかかる。
まず、畑を耕してたくさんのブドウの実がなる木を
育てるのに、15~20年かかるという
(3~4年目からブドウはなるのだが…)。
そして、よいワインづくりに適した
成熟した実が採れるのは、
実の収穫量がピークを過ぎた、
樹齢30年以上の木からなのだ。
(あの世界一のワイン「ロマネコンティ」もまた、
老木から採れたブドウを使っていると
聞いたことがある)。
ことブドウの木に関しては、
古くなるから駄目になるのではなく、
古いからよいものができる可能性が
あるのである。
ビジネスではつい、無意識のうちに
経済効率を考えてしまいがちだ。
如何に時間をかけずに
よいものを手に入れようと…。
しかし、本当によいものをつくるには、
それなりに時間を要するのだ。
また、ワイナリーを開設する際、
醸造設備機器をそろえるだけでも
4,000~5,000万円は必要だという。
しかも最初の20~30年の間は、
ワイナリーだけでは
ほとんど利益にはならないそうだ。
私たちは、経済効率の中で
得たお金でワインを買うが、
よいワインはその効率を求めるだけでは
できないということだ。
これは、人間の成長過程、
ひいては一生にも
共通することだろう。
たとえ、どんなに焦って
効率的に何かを達成しようとしても、
なかなかできないものがある。
私たちは、経済効率を求め過ぎて、
未来の自然や人間らしい時の流れを、
逸脱してしまっているのかもしれない。
時間をかけ、
長期的目線で物事を判断し、
その鍛錬や過程を繰り返さなければ、
よい結果に結びつかないというものは
私たちの周りにたくさんあるということだ。
つまり、人間も50~60歳くらいから
本当に深みのある、味わい深さを発することが
できるのだろう。
はっはっはっはっ、
私もこれからが深みを発揮するとき…。