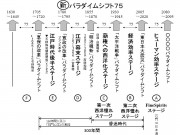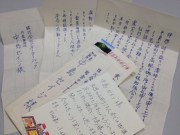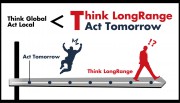10/20
2014

ブレイクスルーのち晴れ
私の自宅を彩る、ボケの花と琉球アサガオ。
やっぱり、花のある空間は心に癒しを与えてくれる。
…あれっ?
でも、花を咲かせるにしては少々季節外れでは…?
そう、実はボケも琉球アサガオも、
死線を潜り抜けてきたのだ。
今ではきれいな朱色の花を咲かせているボケだが、
春先にハダニが発生してしまい大変なダメージを負った。
春を過ぎ、夏を過ぎ、元気を失っていく様子を見て、
もうダメかと半ば諦めかけていたところ…。
なんと、夏の終わり頃から
葉が少しずつ元気を取り戻したのだ。
そして、9月末にはついに一輪の花が!
ボケは見事に復活を遂げた
(これで、来年の春たくさんの葉と花を
つけてくれれば完全復活だ)。
昨年7月の朝顔市で購入した琉球アサガオは、
秋が終わる頃まで我が家の出窓を飾ってくれていた。
そして今年、そろそろ開花時期かと思いきや、
琉球アサガオにもハダニの魔の手が!
即刻ベランダに出し、薬をまいてハダニを退治した。
しかし、一難去ってまた一難!
今度は葉を食う害虫がついてしまい、
葉が穴だらけになってしまったのだ。
慌てて対処したが、一連のストレスで
琉球アサガオはボロボロに…。
しかしそんなアクシデントを経験しながらも、
10月半ばにとうとうオーシャンブルーの花を咲かせてくれた
(2つめのつぼみも開花間近!)。
何ヵ月も葉を落とし、
厳しい状況を過ごしてきた2つの花き。
困難を乗り越えて咲き誇る姿に、
思わずホロリと来てしまった。
毎日水をやっていると、
植物たちの踏ん張りが伝わってくる。
ボケも琉球アサガオも、
間違いなく強くなっているだろう。
私の大好きな言葉に「ブレイクスルー」がある。
障壁を突破して花開くのは、
植物だけではなく人間もそうだ。
日々の中には、大小さまざまなストレスが生じる。
しかしそこで逃げずに立ち向かえば、
ちょっとしたストレスには
しっかり対処できる強さが身に着くのだ。
その姿勢こそが成長の糧となる。
たとえ辛く苦しい真っ暗闇の中を歩いていたとしても、
そこを抜ければ晴れた空が広がっているのだ。
まさに、“ブレイクスルーのち晴れ”ってこと!