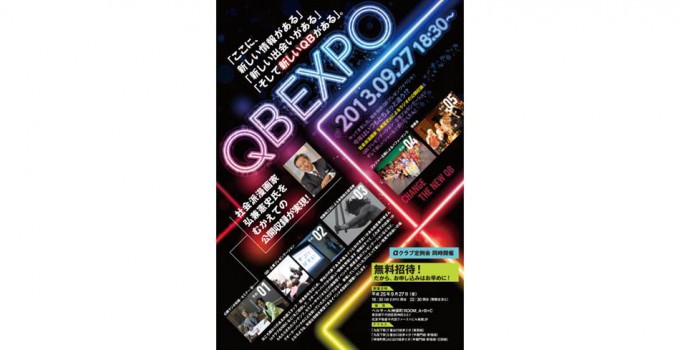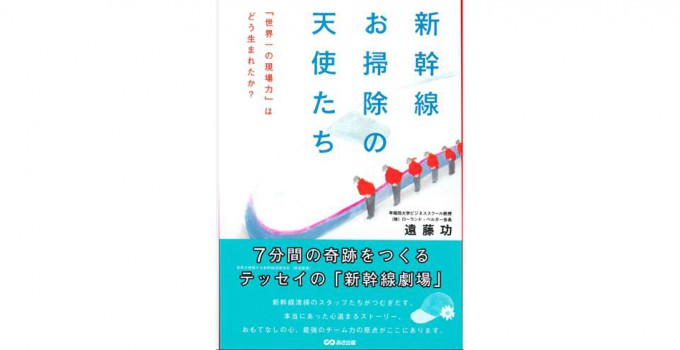09/17
2013

「一事が万事」の飲食ビジネス
「“キムチ”の持って行き方、
お客さまへの出し方でよい焼肉店は決まる!」
…え!? “キムチ”で!?
そんなことを話してくれたのは、
食の演出家である大久保一彦氏。
「このお店は何かが違う」とお客さまに思わせられることが、
また行きたいと思わせ、繁盛のコツになる。
というのが、大久保氏の考える接触デザイン。
ではどうして「よい焼肉店はキムチの出し方で決まる」というのだろうか。
焼肉店ではお肉の注文を受けてからお客さまに提供するまで、
それなりの時間がかかるもの。
その間の場を持たせる料理としてキムチが多く注文される。
そして、その料理をお客さまに提供する
役割のほとんどが若手スタッフとなるのだ。
そしてその若いスタッフたちが、たかがキムチ(されどキムチ)を、
お客さまにどう提供するかがポイントになってくる。
その提供の仕方によって、その店のお客さまサービスの考え方や、
スタッフ教育への取り組みまで
推し量ることができるということ。
まさに「一事が万事」だ。
実は「掃除」も「一事が万事」。
掃除の会のトイレ掃除は道具を並べるところから始まる。
その並べ方や置き場所には、掃除の手順に沿ったルールがあり、
その掃除の手順にもルールがあるのだ。
つまり掃除の会のトイレ掃除は、
ただトイレをキレイにするのではなく、
それを通して段取りの大切さであり、
物事との取り組み方などまで学ばせてくれる。
もっと言えば、掃除と真剣に取り組むことで、様々な気付きが生まれ、
その気付きは色々なものに応用が出来るということ。
これはまさに「一事が万事」の代表的な存在だろう。
さて、大久保氏は、これからの飲食業界は
食材の生産者とお店がもっと近付かなくてはとも。
世界的に見ても、今後は、
生産者とお店が…言い換えれば、
生産者と生活者(お客さま)が
もっと近づいていくと語っている。
「一事が万事」の大久保流飲食業界の
今後のポイントと潮流は、
9/22・9/29の『BUSINESS LAB.』でたっぷりと語られる予定だ。
こうご期待!
──────────────────────
InterFM『BUSINESS LAB.』
東京76.1MHz・横浜76.5MHz
毎週日曜・朝6時から好評放送中!
──────────────────────