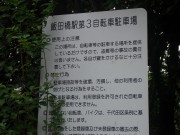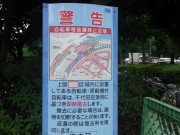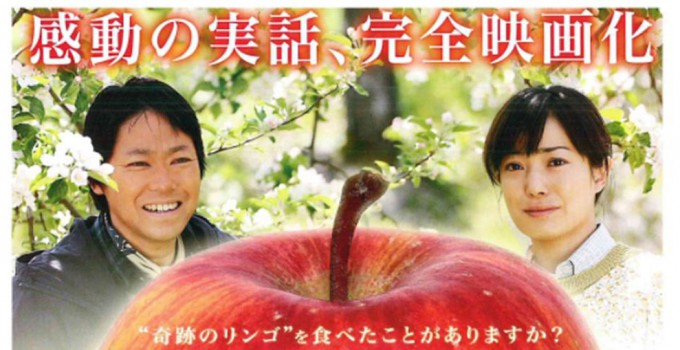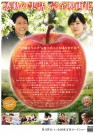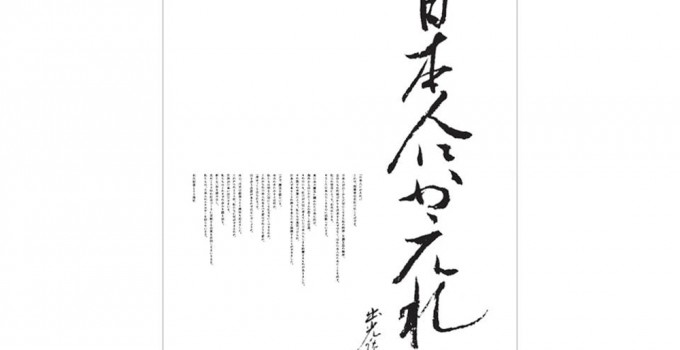07/01
2013
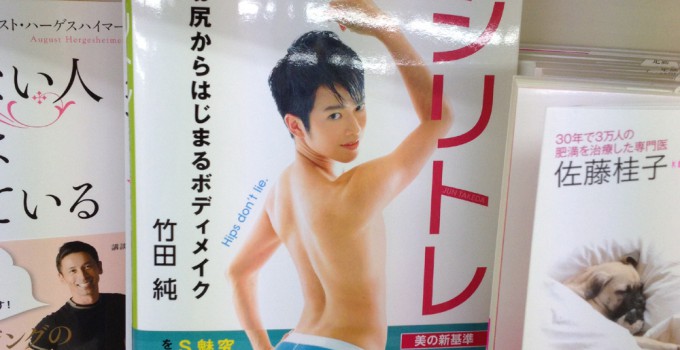
ビジ達流“シリトレ”のすすめ
“スタイルのポイントはヒップにあり!”
…ということで、いま、お尻への注目度が急上昇している
(私は以前から注目してたけど…)。
居酒屋向けにハイサワーが発行した、
美尻モデル写真が登場する「美尻カレンダー」が好評により一般商品化。
“お尻王子”ことバレエダンサーの竹田純氏による
美尻エクササイズ“シリトレ”は本もレッスンも人気のようだ。
普通なら、顔やバストなど正面から見た体型全体に目が行きがちだが、
くるっと背を向けた時におしりが垂れているとなんとも寂しい限り。
もしかしたら、本当に鍛えていることが分かるのは
お尻なのではないだろうか。
ということは、日頃鍛えている私は美尻の部類なんじゃないかな~?
…さて、私のお尻の話は置いておいて、
ここからはビジネスのお尻、ビジ達流“シリトレ”の話をしたい。
そもそも、ビジネスにおける美尻とは?
お客さまから見て、
・頼んだ仕事が良い仕上がりである
・打ち合わせなどでも気持よく仕事ができる
・仕事を通して色々と学べる
・“good job!” と言いたくなる
このように、また次も仕事を頼みたくなるような満足度を高めること。
一見、綺麗な顔やバストをしていても、
くるっと背を向けた時に
美しくないお尻がそこにある企業は意外と多い。
つまり、最初にあれこれできると語っていても、
ふたを開けてみれば
プロセスにおける対応に気配りがなかったり、
色々な点で詰めが甘かったりということ。
これでは、お客さまの満足は得られないし、
今後の信頼もカタチづくることはできないのだ。
案外、美尻ではない会社が多い。
ここがチャンス!
長くビジネスを続けていくためには、
企業の“お尻”、すなわち表から見えない
裏側の部分への“シリトレ”が必要なのだ。
日常の会話の中でも良い情報を発信したり、
打ち合わせなどでも能動的な対応をする。
詰めを甘くしない。
このように見えない部分で長きに渡って
鍛錬しながら努力し続けること。
直ぐに結果に出なくても自己のスキルアップに投資をすること。
それがビジネスにおいての“シリトレ”なのだ。
これらを短期的ではなく、
長期的にかつ真摯に取り組むことで
企業のお尻は美尻へ近づくのだ。
「ローマは一日にして成らず」
建国に500年を要したローマ帝国のように、
絶え間ない努力をすることが、
健康にも、ビジネスにも大切ということ。
「美尻は一日にしてならず」だ!