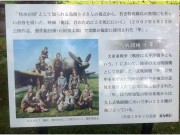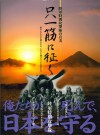05/27
2013

トレーダージョーズの楽しみ方
やっぱり、トレーダージョーズでしょ!
全米に300店舗を構える、西海岸生まれの
人気スーパーマーケット「トレーダージョーズ」。
オーガニック系の商品を扱いながらも、値段は格安。
豊富な品揃えに加え、
ほとんどの加工品や果物がトレーダージョーズブランド、
つまりこだわりのPB(プライベートブランド)として展開している。
独自の商品開発力により、
行くたびに新しい品々がお出迎えしてくれるのも何とも嬉しい。
その地域によって扱う商品も違うらしく、
品揃えもいつの間にか変わっていくということだ。
スタッフのサービスも、他のスーパーとはあきらかに違う。
レジまわりに案内スタッフがいるのはもちろん、
スタッフ一人ひとりが店・商品のことをしっかりと知っていて、
尋ねればきちんと説明と案内をしてくれるのだ。
そこには、セルフサービスの本場アメリカにあっても、
トレーダージョーズ流のサービスポリシーが感じられる。
そんなこだわりの品揃えを可能にし、
しかもお手頃価格できる理由はというと…
「美味しい物を安く大量に直接プロデューサーから仕入れる」から。
トレーダージョーズが掲げる、このシンプルなポリシーを継続し、
徹底してきたことが、結果的に他のスーパーとの
大きな差別化につながり、繁盛店へと成長させたのだ。
だからこそ、未だに安くて美味しい
こだわりのPBを大量に展開し続けられる。
日本にもPBはあるが、これは独自にプロデュースしたものではなく、
有名ブランドと交渉して作ってもらっているもの。
こだわりのない日本のPBは、中島流で言うともはやPBではないのだ!
商品に特徴があり、サービスも充実。
それでいて新商品が続々開発され、しかも割安。
そして何といっても、これら選ばれる全ての要素を支えている
“トレーダージョーズ理念”を、しっかりと守り続けてきたことが、
厳しい経済状況の中でも愛され続けてきた理由だろう。
最近では、この“トレジョ”のエコバッグが
Webで購入可能になり、日本でも大人気だとか。
話を聞いてたら、皆さんも行きたくなったでしょ~?
えっ! 何でこんなにトレーダージョーズのことを今語るかって?
はっはっは、実はもうすぐ行くからなのだ!
アメリカのトレーダージョーズを訪問し、
トレーダージョーズのPB商品と
たくさんの取材情報を持って帰る予定。
再来週には、リアリティあるアメリカ視察の情報が
ビジ達中にモリモリしているだろう。
お楽しみに!