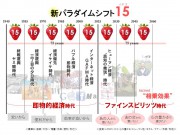06/24
2013
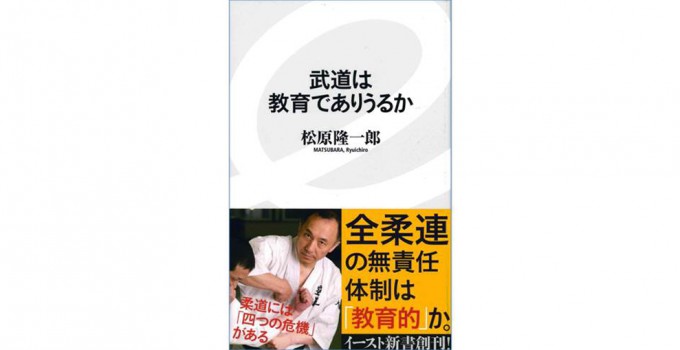
武道は教育でありうるか!?
ついに始まった中学校の武道必修化。
私も柔道を志す者として、
子どもたちが武道を通して、
多くのことを学ぶのは素晴らしいことだと思う…。
…いやいや、思って「いた」かな。
正直に言うと、この必修化は不安要素だらけだ。
おそらく、文部科学省は柔道をはじめとする武道に、
礼儀作法や躾といった教育的効果を期待していたのだろう。
しかし、きちんとした指導法も用意せず、
まさに“丸投げ”状態でスタート。
加えて、ここ数年メディアを賑わせていた、
女子柔道代表監督の暴力やパワハラ、
全柔連の対応の悪さと不祥事、
金メダリストたちの犯罪などの諸問題。
こんな状況で、一体武道から何を学べというのか…
ということになってしまう。
そんな時、たまたま本屋で出会ったのが、
松原隆一郎著『武道は教育でありうるか』だ。
この書籍では、東大柔道部部長である松原氏が感じる、
「柔道の危機」について述べられている。
特に、試合に負けた原因を指導法の問題にせず、
監督もその監督を任命した委員会も責任を取らないという、
“金メダル優先型”の全柔連については厳しく語っている。
私もこのことに関しては、松原氏と同感
(松原氏はそれでも金メダルを獲りたがっていたが…)。
本来の柔道、またスポーツは、結果を優先するのではなく、
日々鍛錬し、仲間と切磋琢磨する過程が作り出す
「人間性」や「人間関係」が大切。
そこから正しい社会のモラルやマナーが生まれるのだ。
つまり“結果よりプロセスが重要”ということ。
まさにここ数年の全柔連は、
目先の金メダル獲得ばかりを優先して(結果獲れていなかったが…)、
プロセスを無視したことで淀み、
腐敗していったと言える(これは柔道だけの問題ではないのだが…)。
この考えをビジネスに置き換えるとどうだろう。
やはり目の前の結果、利益、数字だけを優先していては、
必ずや組織は淀み、腐敗していくのだ。
結果、継続は難しくなるだろう。
また、それぞれの業界において、団体組織をつくり、
ビジネスモデルを固定させ、組織を守り続けようとしては、
業界の新陳代謝が進まず、当然淀んで来ることになる。
“金メダル=すごく偉い”
そうではない。
ここ数十年の経済優先の世の中が生んだ“結果優先型”から、
しっかりとした目的を持った“プロセス主義”へ
シフトする必要があるのだ。
現状の武道(柔道)のとらえ方では、
教育にはならないかもしれない。
しかし、本来武道には十分教育の要素がある。
なんて語っていたら、
1964年の東京オリンピックでのへーシンクvs神永の
決勝を思い出してしまった。
やっぱりあの時のヘーシンクの“柔道”を見習わなければ…。
私たちは、オリンピック種目“JUDO”ではなく、
本来あるべき正しい“柔道”を
もう一度見直すべ時にいるのかもしれない。