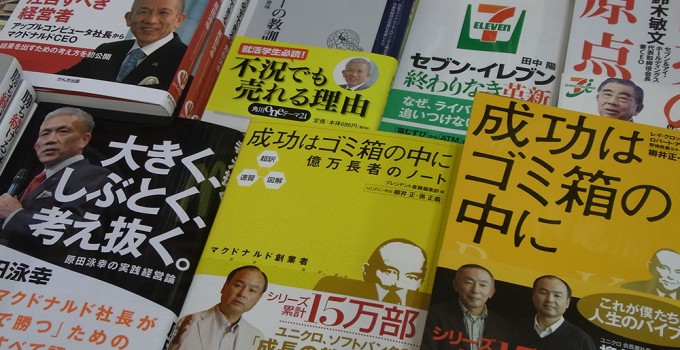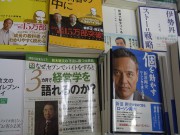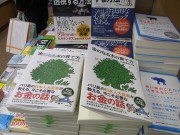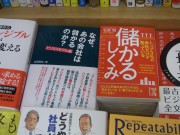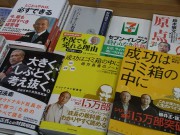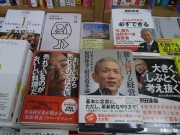03/11
2013

ドジョウ算式相乗効果はどこへ行く
人生は、さまざまな出会いや偶然がハモり
思ってもみない方向で形づくられている。
以前、そんな数々の相乗効果により引き起こされる奇跡のことを
“ドジョウ算式相乗効果”と名づけた。
きっかけは、歩道に生きたドジョウが落ちているのを
たまたま発見して小川に逃がしてやった時の話。
一度市場に出回ったドジョウ
(多分ドジョウ鍋になる運命だっただろう)が歩道に落ち、
私に発見されて…と確率を計算していくと、数々の偶然が奇跡的に
重なっていることを実感したのだ(その確率6561分の1)。
さて、近頃この“ドジョウ算式相乗効果”が
脅かされている気がしてならない!
先日英国で実施された調査によると、
インターネット検索の普及によって
祖父母と孫のコミュニケーションが減少しているそうだ。
孫たちはわからないことがある時やヒントが欲しい時、
祖父母に尋ねるのではなくGoogleやWikipedia、Youtubeを開くという。
つまり、スマートフォンやパソコンに向かって
コミュニケーションをとっている状態だ。
先人(祖父母など)との直接的なコミュニケーションにより、
本来の目的以外の情報やアドバイス、
つまり “副産物”も得られるはずなのに…。
確かにインターネット検索は便利だし、
人に聞くよりも自分で調べた方が早い場合もあるだろう。
しかし、何かのついでに得た情報が、
その後の判断や決断への大きなヒントになることはよくある。
直接的なコミュニケーションの機会をおろそかにすると、
目先の目的だけしか果たせず、相乗効果あるビジネスの展開が
なかなかできなくなってしまうだろう。
プラスアルファがそぎ落とされてしまったら、
人生や世の中の流れまでもが変わってしまうと感じるのは私だけ?
ちなみに、弊社でもちょっと気になることが…。
弊社ではシステム管理のIT化を推進中なのだが、
やはり若い人たちの方がITの活用知識を持っている。
そのため、これまでの“当たり前”であった
「部下が質問して上司が教える」という構図が崩れつつあるのだ。
人との直接的なコミュニケーションが希薄になっていく中で、
上司と部下の立場が逆転し上司の権威が失墜してしまう…な~んてことにも!?
インターネットは確かに便利だが、
その代わりに何か大切なものを失おうとしているように思えてならない!
日々の何気ないコミュニケーションが相乗効果を引き起こし、
結果的に人生が豊かになるのではないだろうか。
“ドジョウ算式相乗効果”は、一体どこへ行ってしまった!?