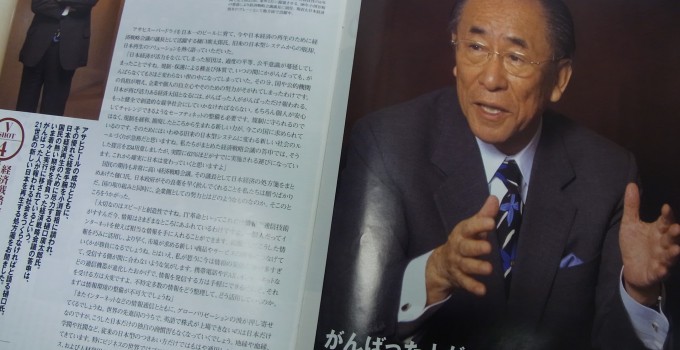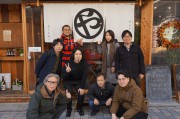01/01
2020

2020年、破壊的イノベーション元年!
2020年、明けましておめでとうございます。
今年も、「ビジネスの達人」よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓
さて、2020年は“破壊的イノベーション”元年!
2020年は誰もが東京五輪と言うでしょうが、
実は2020年から2030年に向けて
さまざまな技術革新によって破壊的テクノロジーが本格的に活躍し、
“破壊的イノベーション”へと進む。
“破壊的イノベーション”って何⁈ という人もいると思うので…
→既存のビジネスであり事業構造の秩序を破壊し、
これまでのビジネスを劇的に変化させるイノベーションのこと。
これまでは、既存商品やサービスよりも高機能、低価格、小型化、
ユーザビリティ(使い勝手)の高さ、簡便さなどを実現させると
言われてきたが、これから起こる“破壊的イノベーション”はちょっと違う。
「5Gの本格的始動」により、
高速・大容量、低遅延、多接続となり、
これまで出来なかった遠隔手術ができるようになるし、
自動走行により交通事故も一挙に少なくなる。
「運転手のいない自動運転」も、限られたエリアだけでなく
数年のうちに公道で展開されることになる。
するとタクシーもトラックも運転手がいなくなるということに。
衛星が充実し、「トラクターの自動走行」があたりまえになれば
農業は劇的に変わり、ITエンジニアより人気の職業になるかも⁈
「AIの進化」と様々な「AIプラットフォーム」の出現により、
あらゆるAIを駆使したサービスがたくさん提供されるだろう。
どんな国に行っても会話には困らないし、
お年寄りの相手も会話のできる「ロボット」が対応してくれることに。
寂しい若者も仮装パートナーが相手をしてくれることになるだろう。
(私もそろそろお世話になるかも…)
「ブロックチェーン」がしっかり機能してくると
どこで稼いでも、どこで売り買いしてもよく、すべてカード決済⁈
スマホ決済となり、円でもドルでもない電子通貨となるのだろうか。
iPS細胞による再生医療により、歯も内臓も再生できることとなり
医療もこれまでから劇的に変わることに。
↓ ↓ ↓ ↓
いかがだろうか。
2020年の今年から、どんどん現実のものとなってくるわけだ。
すなわち、これまで以上にスピードを持って
“破壊的イノベーション”が次から次へと起こってくるということ。
2020年、東京五輪にうつつを抜かしていてはいけない。
“破壊的イノベーション”に対応するべく、
今から準備しようではないか。
そこで“破壊的イノベーション”を想定しての
中島流「Japanese UP-CYCLE」である。
もう行がなくなったので、中島流「Japanese UP-CYCLE」は
この次のビジ達で!
2020年も“破壊的イノベーション”を予告する
中島セイジと“ビジネスの達人”をよろしくお願いします。
さて、今年は“ビジネスの達人”が、YouTubeデビューするかも⁈
乞うご期待!