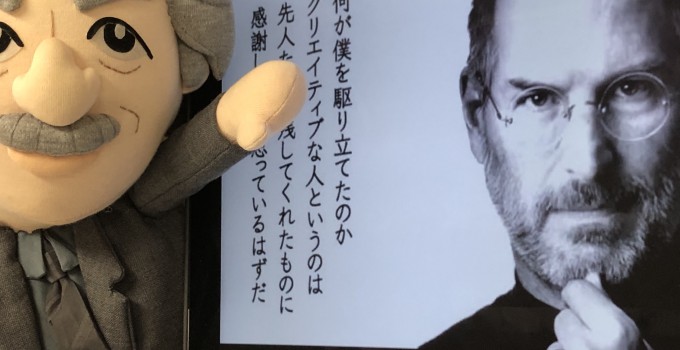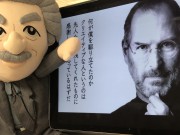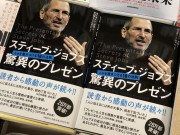10/21
2019
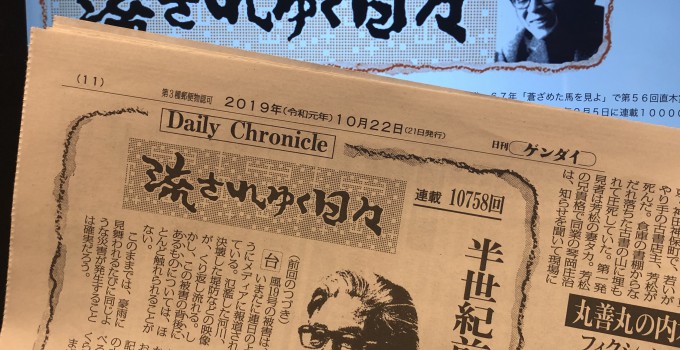
“Vol.850”の持つ意味!?
もうすぐ「ビジネスの達人」が
“Vol.850”を迎える。
これは週刊だから17年目ということとなる。
[ビジネスの達人へはこちらから→ http://bt.q-b.co.jp ]
そして週5本発信を14年ほど続け
この3年くらいは週3本発信としている。
ということで「ビジネスの達人」はもうすぐ
トータル約4,000本発信となるわけだ。
ふっふっふっ、スゴ~い!
「自分を褒めてあげたい」
(どこかで聞いたことのある言葉だが…)
まぁ、こんなところで自画自賛していては
その先は知れたところ。
さて、ギネス記録更新中の「流されゆく日々」
をご存知のだろうか。
このところ風貌が似てきたと言われることもある
五木寛之氏のコラムだ。
(畏れ多い話だが…)
日刊ゲンダイだからのDaily Chronicle。
なんと2019年10月21日の今日で連載10,758回となる。
(スゲ~)
日刊ゲンダイ創刊と同時にスタートしたわけだから満44年。
入社してすぐこのコラムの担当者となったスタッフが、
少し前に定年となったと聞いた憶えが…
40年以上続いているわけだから不思議ではない。
五木氏も連載コラムを依頼されたとき
「毎日の連載ってのは気が重いなあ。週一回でどうですか」
と言ったが、編集長は
「いや、いや、なんでもいいから、勝手に書きなぐってりゃいいんです。
どうせ3カ月か半年でツブれますから」と語ったという。
(五木氏は今年87歳。その編集長も故人となったという)
いや~44年は長いし、その間、時代も大きく変わったということ。
そして「流されゆく日々」のコンセプトも、
時代が流れていくなら、自分も一緒に流れに漂っていこうということ。
この五木寛之氏ならではの時代感覚が、
多くの読者に受け入れられたからなのだろう。
ふむふむ、私たちも時代のビジネスとともに
流れに乗って行かないことには継続は難しいということ。
やっぱり「Grab the Flow,Go with the Flow」なのだ!
それにしてもコラム10,000本は遠い!?
年150本だから、後40年必要で…104歳(´・ω・`)