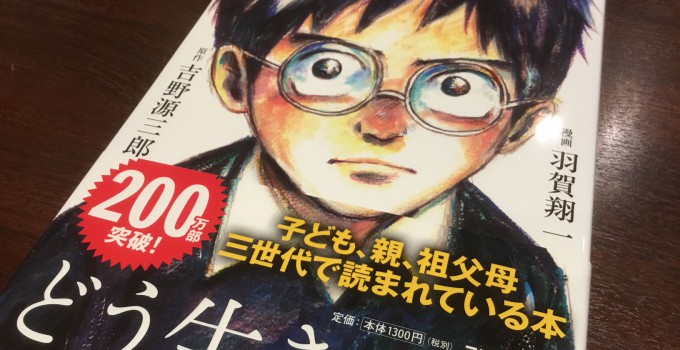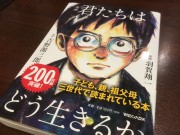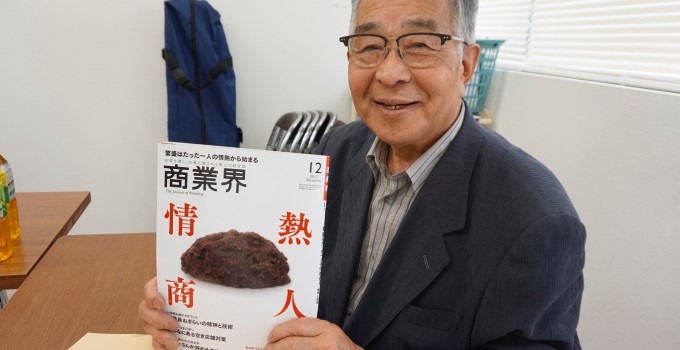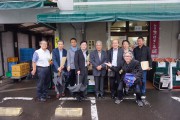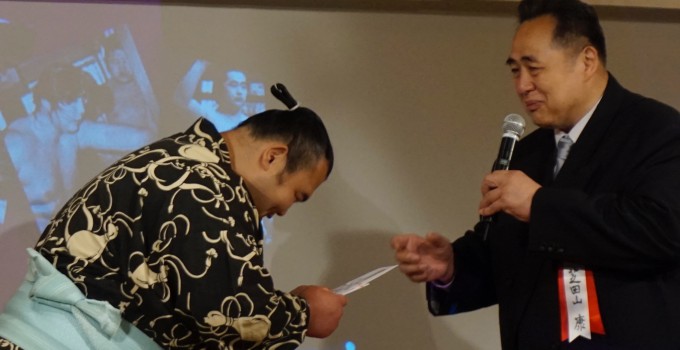07/02
2018

「負ける建築」の流儀
あの建築家の隈研吾さん、神楽坂近くに住んでいるって?!
だから「赤城神社」の設計に関わったんだとか。
そして神楽坂駅前の「la kagu(ラカグ)」も隈氏のデザインだというし...
これらのスポットは私にとっても近所であり良く訪れるわけだが、
言われてみれば隈氏らしいデザインかもしれない。
そう、木材の持つ温かさをうまく活用しているというか、
どこか新しいけれど馴染んでいるというか。
これが隈研吾氏らしさなのだろうが...。
何度か訪れた南青山のあの割りばしで造ったような
パイナップルケーキの店も隈氏らしいデザイン。
新歌舞伎座も、根津美術館も隈氏設計で、
そして新国立競技場もとなる。
いや~とにかくこの頃は、 あちこちで“隈研吾氏設計”を耳にする。
そして実際に目にするそれらの建築物にも当然だが共通点がある。
その共通点とは、隈氏的に言えば「負ける建築」 ということなのだろうが...??
はたして「負ける建築」とはどういうことなのか。
「勝つ建築」に対して「負ける建築」と言えばわかりやすいかもしれない。
すなわち、これまでの周囲の環境を圧迫してきたのが「勝つ建築」で、
周囲の環境になじみ、さまざまな外力を受け入れ、
柔軟に対処しながらも独創性あるものへと展開するのが「負ける建築」ということ。
う〜ん、この「負ける建築」とは、隈氏ならではの独特の表現なのだろう。
言われてみれば「赤城神社」も「ラカグ」も
周囲の環境に馴染んでいながらもどこか独創的なところも兼ね備えている。
そして、どちらも多くの人たちがいつの間にか集まってくるのだ。
(これが負ける建築のスゴいところかもしれないが…)
実は予算や敷地など「制約」を逆手にとって
独創性を生み出しているとも隈氏は言っている。
確かに、さまざまな制約であり条件は、
私たちのクリエイティビティを刺激して、
よりこれまでにない発想へと導いてくれるのだ。
ふっふっふっふっ、これぞクリエイターの存在価値であり、
「負ける建築」の意義。
この隈研吾氏のチャレンジ精神こそが、
建築家でありクリエイターとしての
“存在価値”を創り出しているということ。
だからどんどん無理難題にチャレンジしない限り、
自分の“存在価値”は見えて来ないということなのだろう。
えっ、隈研吾さんって同い年かぁ~。
(いつの間に差がついたんだろう…)
私もクリエイターの端くれ。
“存在価値”のため、まだまだチャレンジ&チャレンジ。
よし…この「負ける建築」に対抗して
「負けるプロジェクト」「負けるプレゼン」ていうのは…
(これじゃ本当に負けちゃいそうだし…)