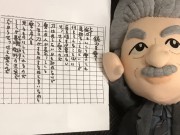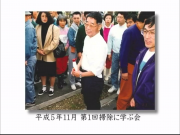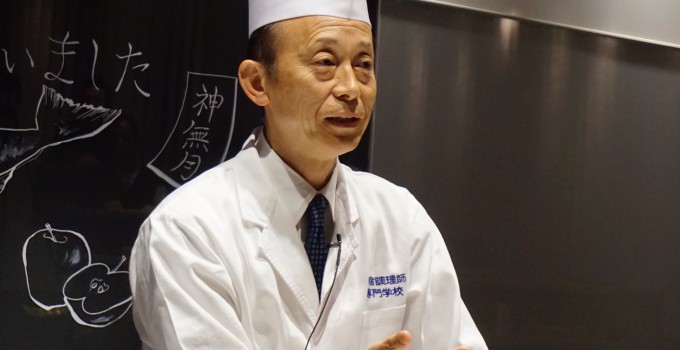10/30
2017
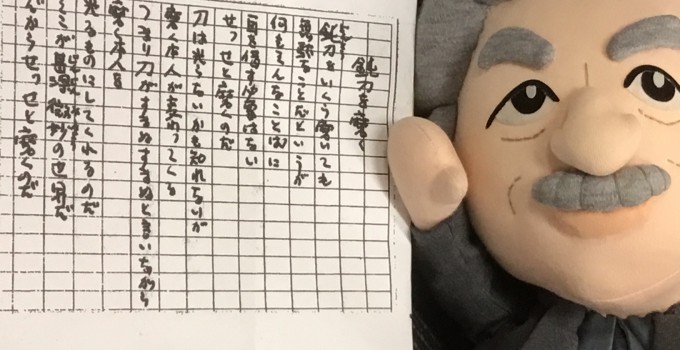
鈍刀を磨く
小学生の頃、家の居間で逆立ちの練習。
誰もいないとき、せっせと練習。
やっと5秒ほど立てるようになったのは…
1,000回?いや2,000回目?
いや5,000回目だったかも。
その年齢の頃、内村や白井は3回ひねり頃だったろう。
でも、でもだ60代の今も逆立ちができるのだ。
(はっはっはっ…)
小学3年で柔道を始めた。
けっこう好きだったが、身体が小さかったこともあり、
なかなか結果に結びつかない。
しばらく、柔道着に袖を通さない日々が続いたが
大人になってから近くの道場に通うようになり、
25歳の頃やっと国体の県の強化選手になれた。
やっとだ。
そして、50代まではときどき講道館に通っていた。
(いまも乱取りは十分できると思うがケガが怖い…)
高校生の頃、新聞配達をしていて、
毎日の配達の後、一面と社説だけ読んでいた。
お陰様でいくらか社会がわかった気になり、
理屈っぽさだけが身についたような…
いや、もしかしたらそれがあってこの仕事になったのかもしれない。
14年間この“ビジ達”(週3~5本のコラム)を発信し続けて来たが、
文章力はご覧の通り…(なさけない…)
そんな時、坂村真民先生のこんな詩が私の手元に舞い降りた。
タイトルは「鈍刀を磨く」。
鈍刀をいくら磨いても
無駄なことだというが
何もそんなことばに
耳を借す必要はない
せっせと磨くのだ
刀は光らないかも知れないが
磨く本人が変わってくる
つまり刀がすまぬすまぬと言いながら
磨く本人を
光るものにしてくれるのだ
そこが甚深微妙(じんじんみみょう)の世界だ
だからせっせと磨くのだ
何か救われる気分になったのは私だけだろうか。
まだ振り返るには早いけど、まさに“鈍刀”。
この肉体も頭脳も鈍刀だったのかも。
でも感謝。
この肉体と頭脳に感謝。
そのお陰で“あきらめないしつこさ”だけは身についたのだ。
だから、まだまだせっせと磨くのだ。