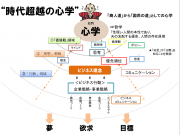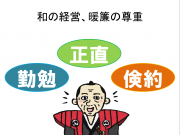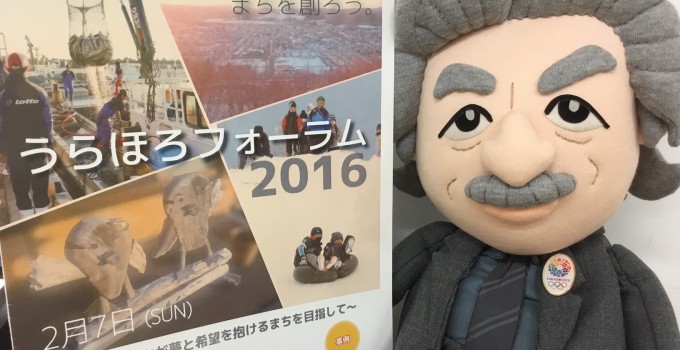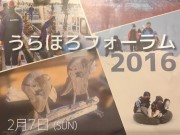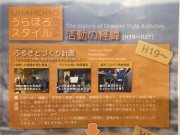03/14
2016
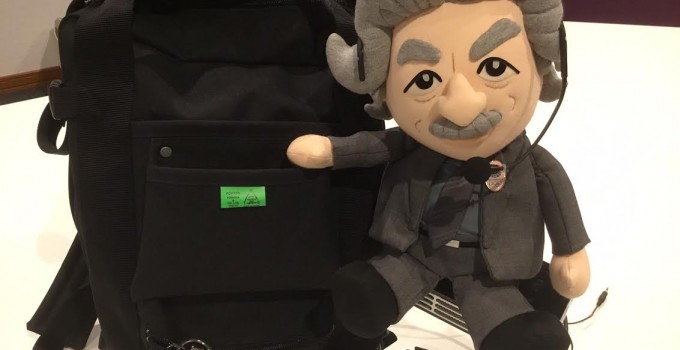
“用の美”を引き出す
先日、バッグにいつものように仕事道具をあれこれ詰め
込んで、遠出をしようとしていた矢先…。なんと、バッ
グの底のところが綻び、中身が見えようとしているでは
ないか…(あちゃ~)。まぁ、バッグを新調してから3
年以上経つわけで、あちこちユルくなっていたのも確か。
急遽新しいバッグに変更することに。
(えっ、別のバッグが用意されている!? なんて思う人
もいるだろうが…)
はっはっはっ、これがきっちり用意されているんだなぁ
~。転ばぬ先の杖、用意万端…。
実はバッグがそろそろ替え時かなぁ~と思っていたこ
ともあり、所用で表参道に行っていた際、近くの吉田カ
バンの旗艦店を思い出し、立ち寄っていたのだ。(さす
が、ぬかりない!)ということで新品のバッグに差し替
えて、出張へ行くこととなった。
やっぱり新品はいいねぇ~。いつもより気持ちよく家を
出たということ。小さい頃から新品を活用するときは、
ワクワクする。“女房と畳は新しい方が良い”なんて諺
もあったくらいだから…(この諺、危うい諺だこと…)。
確かに子どもの頃は、めったに新しいものを買ってもら
うことはなかった。家族の中で、一番下っ端だったこと
もあってだが。
その頃から、お下がりでないもので自分のものと言える
新品を身につけたり、利用したりするときはちょっと興
奮した記憶がある。そして、長~く使うわけだが…。
とにかく、新品のバッグをかついで、いつもより気持ち
よく家を出たということ。
今回は“新しいものはいい”という話ではなく、この用
意されていた吉田カバンのバッグ、何と私にとっては7
代目なのだ。1代で3年は使うので、約18年くらいこの
バッグのお世話になっているということ。吉田カバンは
生地もデザインも変わらず、同じものをつくってくれて
いるのだ。それがよくて、私は18年以上ず~っと活用
させてもらっている。やっぱり、いいものはいいという
こと。
出先や出張先でもこのバッグを背負いあちこち歩き回
る。ipadから紙の資料、さまざまな小道具まで押し込み、
動き回っても、丈夫で型崩れしない。そして、使い良さ
だけでなく、デザイン性もすばらしいのだ。
ある仕事で「用の美」という言葉に出会ったことがある。
その見た目の美しさだけでなく、機能はもちろん、活用
することでより愛着が湧いてくるものの美しさとでも…。
まさにその“用の美”がこのバッグにあるように思えて
ならない。本当に美しいものは飽きないし、陳腐化しな
いということ。まぁ~人によって“用の美”は違ってく
るということかもしれないが、長く使い続けたいものに
はこの美しさが存在するということだ。
ここで、そんな女性に出会いたい…なんて言うと、また
皆さんから袋だたきにあうのでやめておくが…。
“用の美”を引き出すには、使う側にもそれなりのマナ
ーと愛情が必要ということだろう。何事も継続には、一
方通行ではなく、互いのバランスが必要ということだ。











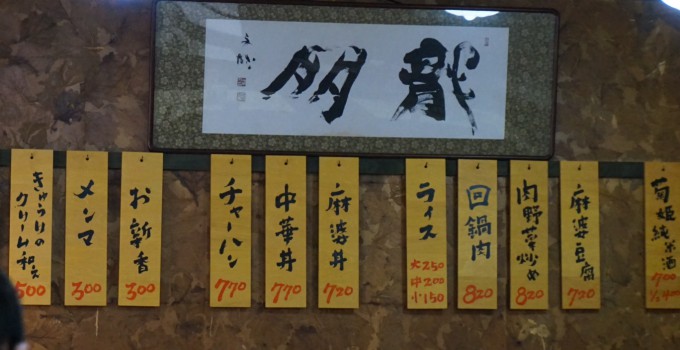




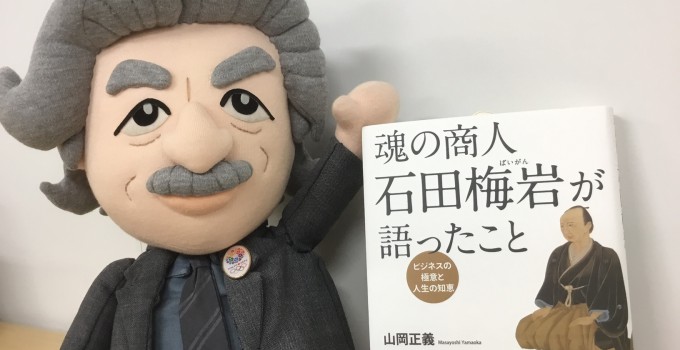
![moba[1]](https://bt.q-b.co.jp/wp-content/uploads/2016/02/moba11-180x91.jpg)