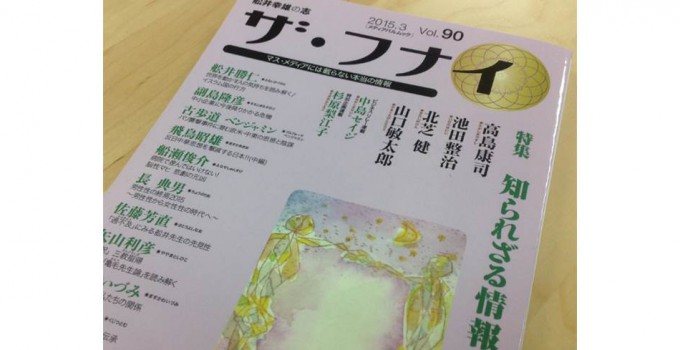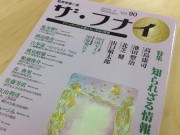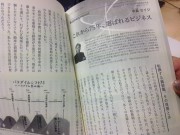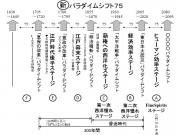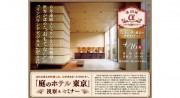03/16
2015

中里流まち工場の仕事道
「社員数は上限28名と決めている」。
そう言いきるのは、
全国47都道府県すべてに取引先を持っている
中里スプリング製作所の社長・中里良一氏。
中里スプリングは、6800種類以上の
精度の高いバネをつくっている町工場。
その中里社長の経営方針を聞くと、
実に独特な価値観をもっていることがわかる。
たとえば、「嫌いな取引先は切ってよし!」。
社長は、酒やゴルフ、カラオケなどを
むやみに誘ってくる企業とは取引しないという。
これだけでも、普通とは違う会社、
いやむしろ非常識な会社とも言えるだろう。
しかし、そうした経営方針であっても仕事は増え続け、
社長就任時点では、15社ほどだった
取引先が、1700社以上に成長したのだ。
また、仕事の請け方も、ひとつの取引先に
大きなウエイトを置かないようにリスクを分散しているという。
一見、非常識に見える経営方針も、十分考えられた発想なのだ。
それは、中里スプリングで働く社員が
働き易い環境づくりを追求し、
さらに良い経営状態を維持するためなのだ。
良い環境づくりを表す具体的な例がある。
それは、年間を通して一番の評価を受けた社員は、
会社の設備も仕事時間も自由に使って、
つくりたいものをつくってよいという制度。
また、地方の町工場ということもあり、
たとえ社員の平均点は低くても、
光る長所をしっかり伸ばしてもらう。
足りないところは、みんなで補えばいいのだ。
こうすることで社員の存在理由も醸成することができ、
イキイキと仕事ができる環境をつくれるということ。
非常識に見えるが、
理にかなっている経営なのだ。
中小企業であり町工場だからこその規模を
活かし、社員のモチベーションも
維持しながら安定した経営を続ける。
これこそ、中里流“まち工場の仕事道”なのだ。
そんな中里氏の仕事道がたっぷり聞けるラジオBUSINESS LAB.は
3月22日、29日(日)それぞれ朝6:00から!
ぜひぜひ聴いていただきたい!!