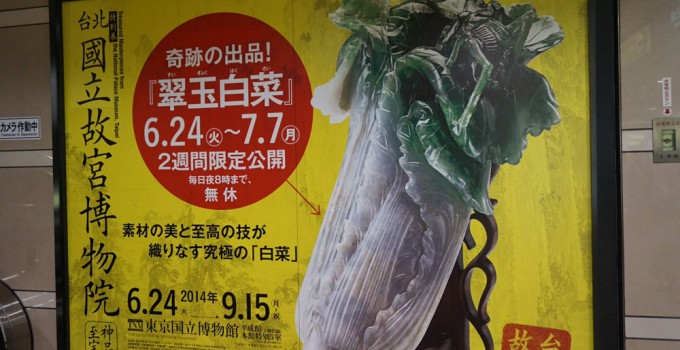07/07
2014

すばらしい“おもてなしの心”
「ありがとうございます」とキップを受け取り、
チェックをする。そして、
キップの向きを変えながら
「いつも、ありがとうございます」
と静かなトーンで言うのだ。
えっ!? “いつも”…思わずもう一度
車掌さんの顔を見直してしまった。
この静かなトーンでの“いつも”
が感謝の気持ちが込められているようで
心地よく感じられたのだ。
たぶん、裏付けはなく、
“いつも、ありがとうございます”
と“いつも”の3文字を付けたのだろうが、
これが私たち客には響く。
(その昔の新幹線の車掌さんには
まず期待できない事が…)
話しは変わって、飯田橋駅近くの
三州屋の女将のこんな投げかけ。
「今日は何するの?! いつもの焼きと煮付け?」
一見つっけんどんな口調なのだが、
この言葉にも客として心地よさがあるのだ。
この三州屋は拙著「儲けないがいい」
にも登場する、
昼時だけで4~5回転する定食屋の繁盛店。
もちろん、出される魚料理もおいしく、
ここにも繁盛の要素はあるのだが、
私は女将の何気ない言葉に
繁盛の理由があるように思えてならないのだ。
えっ!? その女将は美人かって!? …
(まあ~女将はこのビジ達見ないし…)
まあ~そこには繁盛店の理由はないと…
(ゴメンナサイ)。
それはともかく、私がここで注目するのは、
この女将の言葉の内容ではなく、
トーンやその言葉の裏にある思いやり。
すなわち、“おもてなしの心”なのだ。
先に紹介した車掌さんも同様、
“おもてなしの心”が“いつも”
に表現されていたということ。
重要なのは“お・も・て・な・し”
ではなく“おもてなしの心”。
言葉の内容ではなく、お客さまに対する
“もてなしたいという心”なのだ。
いまどきの生活者は、カタチだけの
“おもてなし”については、
十分わかっていると言えるだろう。
だから心のない、
儲けたいだけのビジネスはもう通用しない。
これからのビジネスは“オモテ”
ではなくそのウラの“心”
の方が大切なのだ。
これは“暗黙知”の時代とも言えるだろう。
すなわち即物的時代から
“ファインスピリッツの時代”
にシフトしてきたということだ。
それにしても、このところの新幹線の
乗務員の対応は、その昔とは大きく
変わってきた。すばらしい!