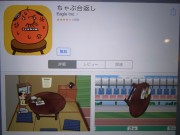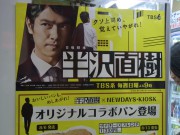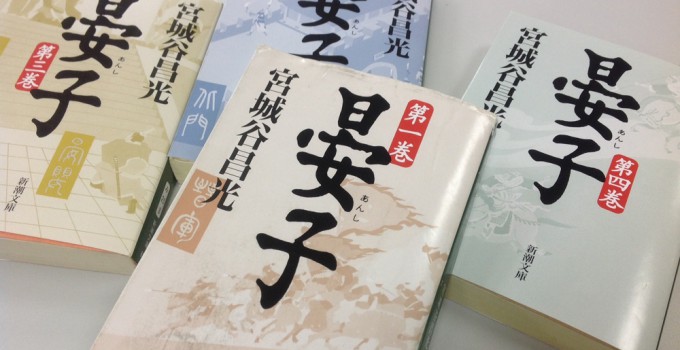10/28
2013

今や、懐かしい“ちゃぶ台返し”
そう言えば、私の小さな頃は家族7人が
少し大き目のちゃぶ台で食事をしていた。
当然、座る場所も決まっていた。
奥のところにご飯の釜とみそ汁の鍋が。
その左右におばさん(母の姉)と
ばあちゃんが(給仕役)、その横におじさんが、
そして母で兄で・・・。
先日の服部幸應先生(服部学園理事長)が
語っていた通りだったのだ。
正座をしてみんなが席に付くのを待ち、
「いただきます」をしっかり言い、食べ始めていた。
そして、二杯目には、「おかわり」といい、
おばさんにご飯をよそってもらっていた
(居候的立場だったのでそっと出していた!?)。
ひと通り、食べ終われば「ごちそうさまでした」と言い、
自分の食器などを持って席を立ち、
流し台の所定のところに置きに行く。
ん~~確かに、このちゃぶ台を囲んでの
家族での食事のときに、ばあちゃんを始め
大人から行儀(マナー)を習い、
食材や料理の知識も得、そして家族たちの情報の
アップデート(近況報告)もしていたのだ。
これが、服部先生が語り続けてきた
“食育”だったということ。
いま思うと、さすがの服部先生
なればこその“食育”発想だったと思う。
しかし、残念ながら、いまや核家族化が進み、
そしてみんなで食事する機会もかなり減ってしまった。
親もきちっとした行儀作法を
教えられる知識も権威もない状態。
そして、子どもは食事をしながら
スマホをいじくっている始末。
これでは、行儀作法どころではない。
昔のお父さんなら、子どものその姿を見て
ちゃぶ台をひっくり返したいところだが…。
そこで星一徹(巨人の星)のちゃぶ台の
ひっくり返しシーンがアタマに浮かぶ。
そう、飛雄馬がちゃぶ台と共に
もんどり打つほどのちゃぶ台返しだ。
残念ながら、いまどきの食卓はひっくり返すにしては
ちょっと重く値段も高いダイニングテーブル。
そして、当のお父さんも星一徹どころか、
明子姉ちゃんの役もできない程、軟弱化している状態。
これでは、これからの家族はどうなってしまうのか。
そんな中で育った子どもたちが展開するビジネスは
どうなってしまうのか。
これからのビジネスをかたる者として
不安な限り。
あ~~~。日本の未来に暗雲が・・・。
そこで・・・。
お父さんはちゃぶ台はひっくり返せないが
決死の覚悟で子どもに言う。
「お父さんの話も聴かず、な、何をやっているんだ!」
「あ~これ、いまスマホのゲームで“ちゃぶ台返し”ってやつ」
「なに~~。ちゃぶ台返し!?ちょっとお父さんにもやらせてくれ!」
なんてね…。おしまい。