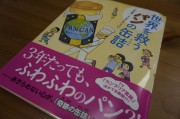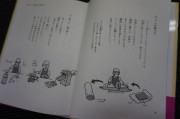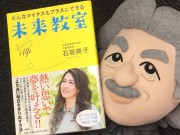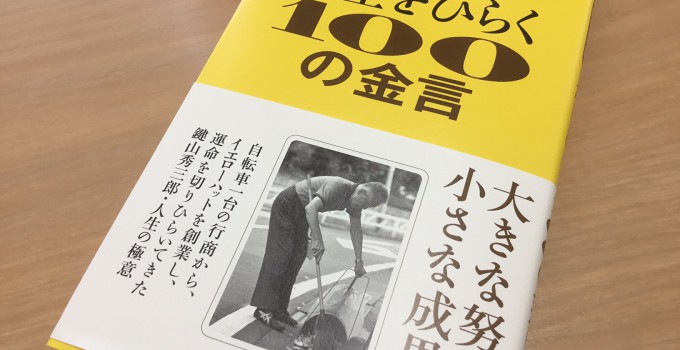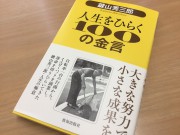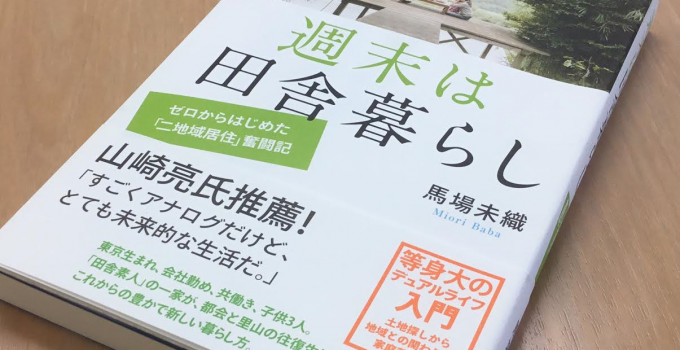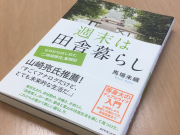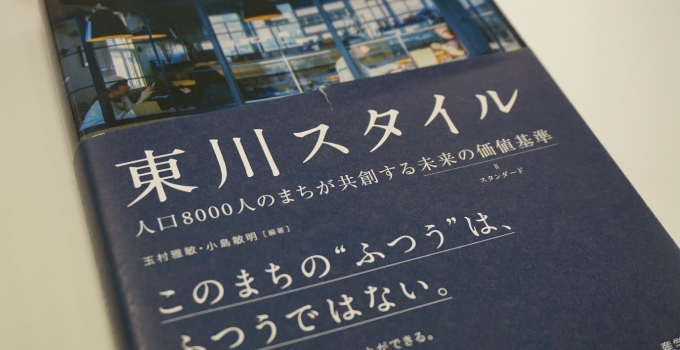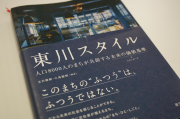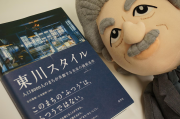11/06
2017

世界を救うパンの缶詰
このタイトルを聞いただけで、
ビジ達を読んでいる方ならピン! とくるかもしれないが…
あの、パン・アキモトの“パンの缶詰物語”が
ついに児童書になったのだ!
(パチパチパチ~!)
この本では、パンの缶詰がどのように生まれ、
世界にどう貢献しているのか…ということが
しっかりと語られている。
パンの缶詰が生まれたきっかけは、阪神淡路大震災。
被災地支援のためにトラック1台分のパンを届けたものの、
その扱いに手間取っているうちに日が経ち、
約半分しか被災地の人々に食べて貰うことができなかったという。
そこで頭を捻り、日持ちに左右されず
被災地でもおいしく安心して食べられるパンとして
開発されたのが、このパンの缶詰だ。
(うんうん、ストーリー性があるねぇ~)
しかし、しかしだ、おいしいパンの缶詰ができたのに、
これがなかなか思うように売れない。
(あるある、こんなことって…)
そこで「もっとパンの缶詰を知ってもらおう!」
その一心で、栃木県那須塩原市の
市役所に缶詰を寄付することを決め、
さらに市役所への贈呈式までも企画したという。
この社会性ある発信が注目され、
多くのメディアに取り上げられることになったのだ!
これはまさに、秋元社長が言うところの“社会性のふりかけ”である。
“社会性のふりかけ”をかけることで、
メディアに注目され、多くの人たちに発信されることになったのだ。
このように直接的に商品を売り込むことよりも、
商品の持つ社会的可能性に照準を当て訴求する、
パン・アキモトの“先義後利”のビジネス姿勢が、
より多くのメディアに取り上げられることになったということ。
特にパン・アキモトなれば、そのビジネスモデル
“救缶鳥プロジェクト”はまさにそれ。
これは、家庭や学校、自治体などで備蓄されたパンの缶詰を
賞味期限を1年残して回収し、
世界の飢餓地域に持っていく画期的プロジェクトだ。
いや~、改めてここまでの道のりをたどってみても
その物語性は大いにある。
このように、今となっては、世界でも活躍しているパンの缶詰 !
まさに“プレミアムな先義後利”の商品といえるだろう。
さて、私が着々と進めている“MEMUROワインヴァレー構想 ”。
地域づくりや街づくり、農業改革を目的としているこの構想だが…
ここでも“プレミアム感ある先義後利”の展開はできないだろうか!?
これが、これからの私の課題といえるだろう。