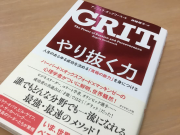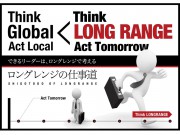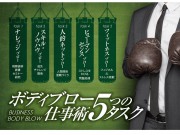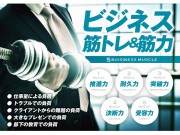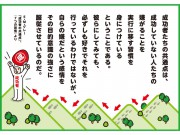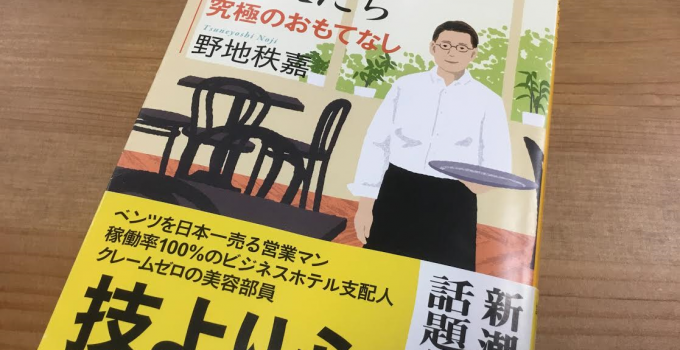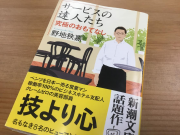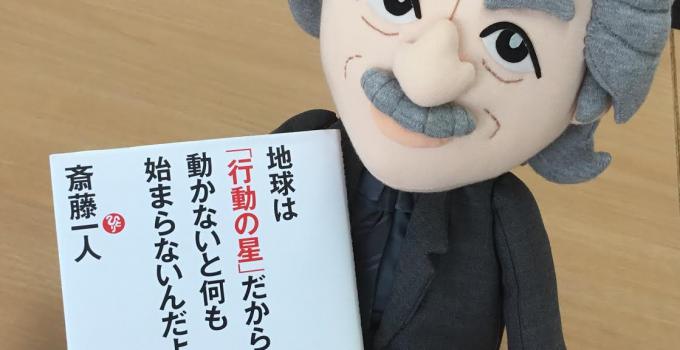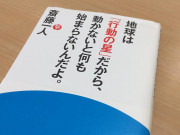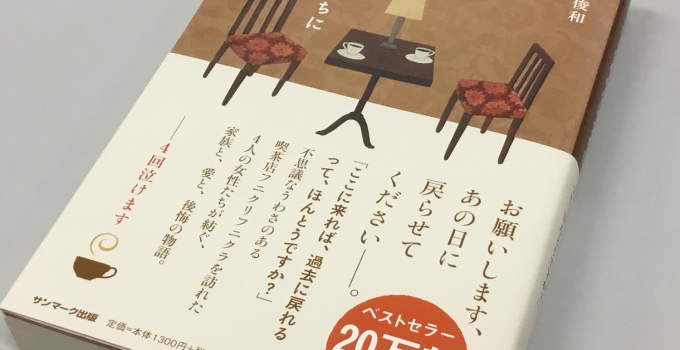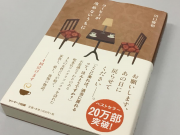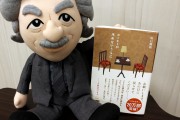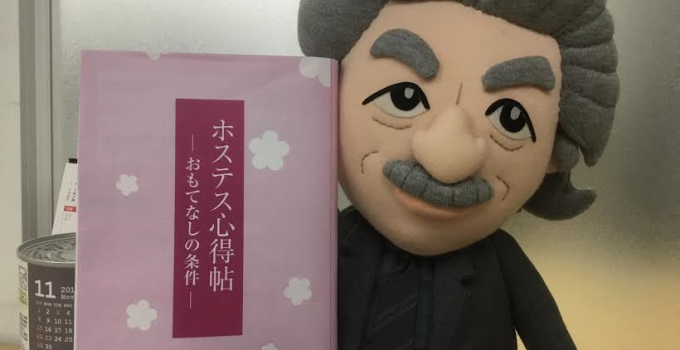10/31
2016
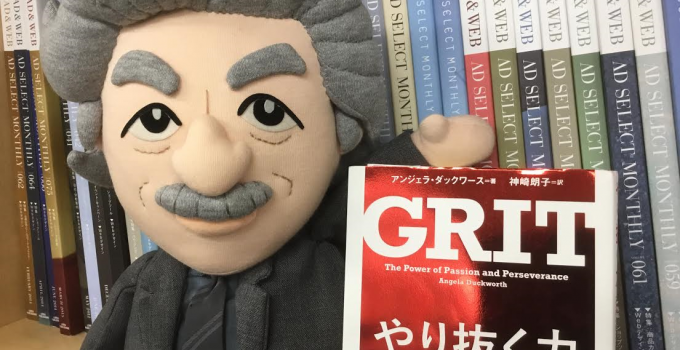
『“GRIT”やり抜く力』アンジェラ・ダックワース・著
副題は、『人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける』。
有楽町の三省堂書店に立ち寄り
いつものように本を物色していたところ、
なぜか、この本が手に取ってほしいと私を引き寄せたように思えたのだ!
人間は本来持っている能力の10%ほどしか使っていないと
聞いたことはあるが、
この本では、人が持っている能力を活かすのは
“GRIT(やり抜く力)”だという。
すなわち“GRIT”さえあれば、
もっと潜在能力を活かせるということなのだろうか…。
この本によれば、「人間は誰しもはかり知れない能力を持っているが、
その能力を存分に生かし切ることができるのは、
ごくひと握りの並外れた人びとに過ぎない」。
つまり、“GRIT”を持っているのは
その「ごくひと握り」の人というわけ。
著者であるアンジェラ・ダックワース氏は
さまざまな事例やアンケートのデータから、
“GRIT”がいかに大きく成功へ影響するかを具体的に証明している。
「グリットスケール」なるその人のやり抜く力を測る
アンケートもあって、読者は思わずやってみてしまうだろう。
人はつい天才を評価してしまい、努力家を評価しない。
成功者について評価するときも才能に着目するが、
“GRIT”についてはほとんど評価されていないのが実際だという。
この本で取り上げられている成功者の事例のほとんどは、
粘り強く諦めないことが結果として、
成功に結び付いているというものだ。
(これには私も同感!?)
実のところ、私も自分の能力が高いと思ったことはほとんどなく、
評価してもらうには人以上にやるしかないと思って
やってきた人間なのだ。
だから…待ってました!
やっぱり大切なのは情熱であり粘り強さ、
すなわち“やり抜く力”だよねぇ~! と言いたいところ。
話は本からずれるが、私がこのところビジ達で発信してきた
“ロングレンジの仕事道”や“ボディブロー仕事術5つのタスク”。
“ビジネス筋トレ&筋力”に“複雑系⇒積小為大”、
そして“成功者たちの共通点”…。
これらはすべて“GRIT”のための要素といえるだろう。
この本によれば、
偉大な人と普通の人の決定的な違いは「動機の持続性」であり、
情熱と粘り強さ、この二つが結果として“GRIT”につながってゆくという。
このやり抜く力をいかに確かな自分のものにしていくか。
それが、世の中でいわゆる成功者となるために
必要不可欠なパワーなのではないだろうか。
この本に出会い、私が今までビジ達で発信し続けてきたことは
やはり間違いではなかったのだと、改めて確信したのだった!