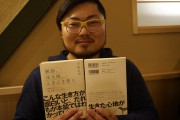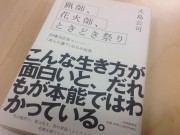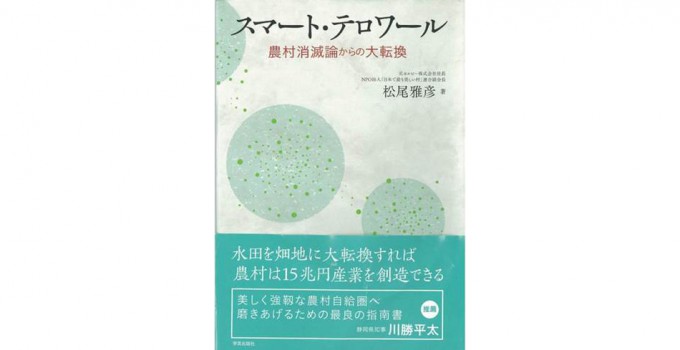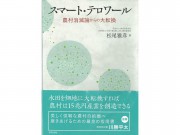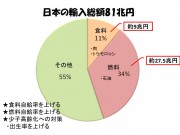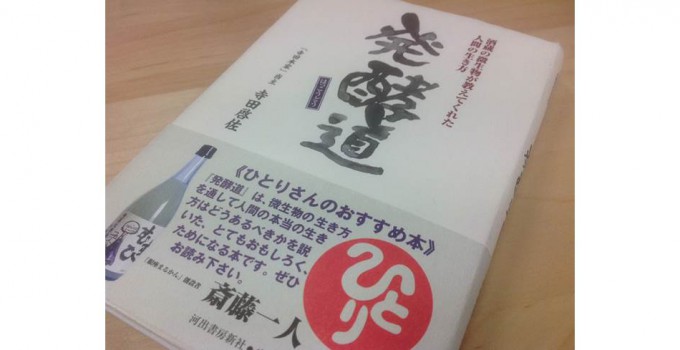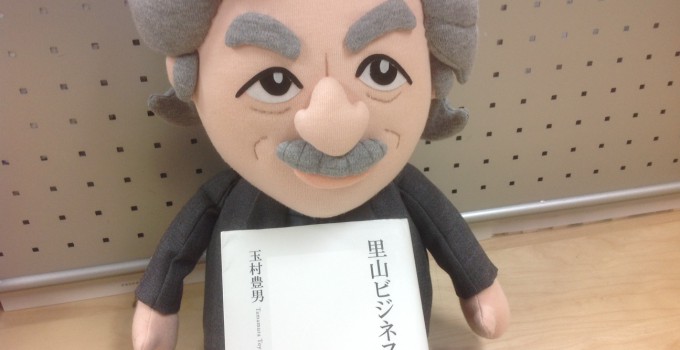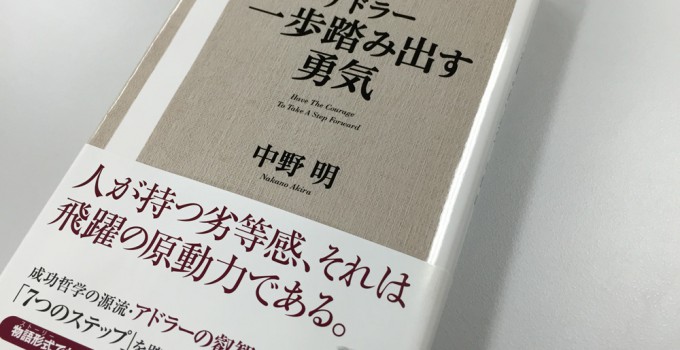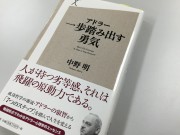02/16
2015
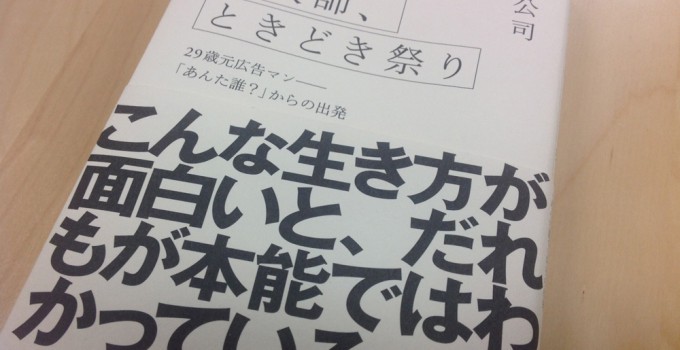
『猟師、花火師、ときどき祭り』大島公司・著
「あんた誰?」からの出発だった――。
そう表紙に綴られているこの本の著者・大島公司氏は、
もともとは大手広告企業で働く
サラリーマンだったそうだが、
その後180度違う世界に飛び込んでいく。
契機となったのは、東日本大震災。
会社を退職したばかりだったこともあり、
すぐに宮城県石巻市へ向かい、
復興支援に勤しんでいたそうだ。
そこで、何もできない自分を改めて知ることに。
そんな中、町の人々の神輿への期待感を耳にし、
大島氏は世話人として祭りを再開させる。
そんな活動へのチャレンジから話の幕があがっていく。
夏祭りのフィナーレには、
打ち上げ花火のイベントがある。
祭りの準備から本番まで走り続けた大島氏は、
夜空に打ち上がった花火に心を揺さぶられたという。
ならば、来年は人の心を動かすことのできる
自作の花火を打ち上げたいと決心することになる。
そこで大島氏は、花火師になるための活動に着手。
制作しているうち、
素材へのこだわりも出てきたというのだから、
本腰をすえて取り組んでいた姿が想像される。
とにかく目の前にある興味と課題に
次から次へとチャレンジする大島氏。
さらには、狩猟免許を取得することに。
なんと猟師にもなってしまったのだ(スゴ~イ!)。
滞在していた石巻市の周りには
豊かな里山が広がっているため、
シカなどが獲れるそうだ。
先日、大島氏にお会いした際、
実際に獲ったシカの肉を持参されていた。
獲るだけではなく、さばいて、
おいしく食べることが大切だという。
広告マンだった大島氏は、
石巻市での生活を通して、
祭りのプロデュースから、
花火師と猟師のスキルまで身につけることに。
それが功を奏し、
フランスの町と石巻市を結びつける活動に繋がっていく。
ついにはフランスで日本のお神輿を担ぎ、
日本の祭りを披露!
世界に日本文化を発信しているという訳だ。
この本を読み、実際に大島氏と
お話させてもらって私が感じたこと。
それは、まさに日本本来の価値観に軸を置きながら
“生きる”ことを体験しているということ。
いい大学を出て、名のある企業に就職しながらも、
その肩書きを捨ててまで選んだ石巻市での生活。
都会では身に付けられない実体験の数々は、
これからの時代を地に足つけて生きていける、
かけがえのないエナジーを得たのではないだろうか。
30歳となる大島氏だが、
躊躇なくその現場に飛び込み、
体当たりで取り組む姿勢が
多くの人々の共感を得ているのだろう。
そんな大島氏は、
5月にInterFM『BUSINESS LAB.』に登場予定。
乞うご期待!