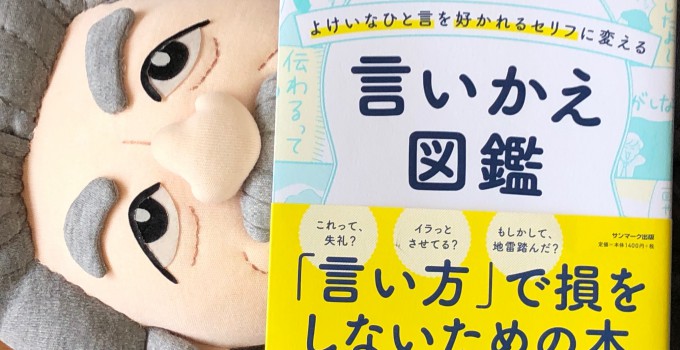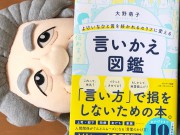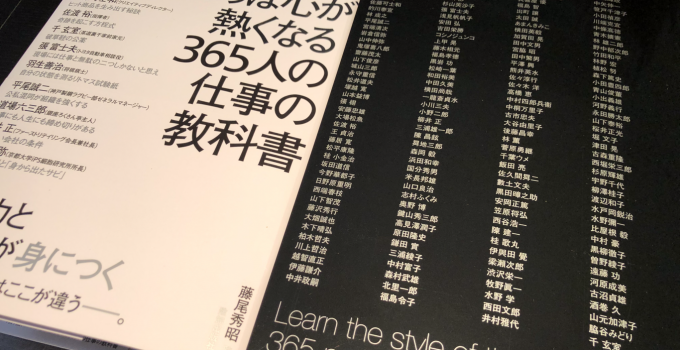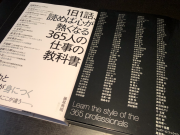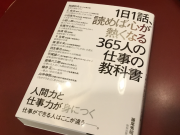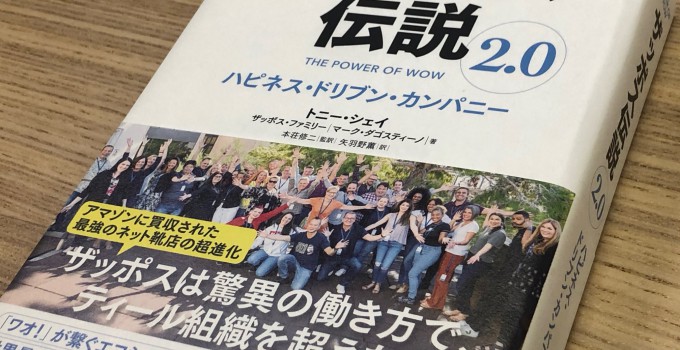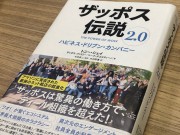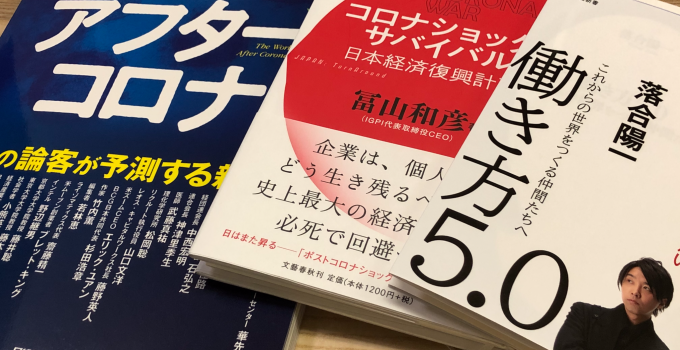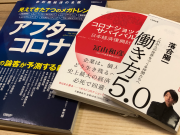05/31
2021

清風掃々WEBマガジン“ONE by ONE”
ついに“日本を美しくする会”のWEBマガジン“ONE by ONE”が
公開された。
“ONE by ONE”とは“日本を美しくする会”の鍵山秀三郎相談役の、
「一つ拾えば一つだけきれいになる」という言葉から
“ひとつずつ”という意味で名付けた。
“清風掃々”は“日本を美しくする会”のメンバーと賛助会員、
国内の“掃除に学ぶ会”に配布されている機関誌で
おおよそ5000部発行されている。
これまでもこの冊子が、“掃除に学ぶ会”から
その先の人たちにどのくらい配布されているかが疑問だった。
5000部印刷しても、本当の意味で“掃除”に興味を抱いた人たちに
届いているかどうか・・・?と思っていたわけだ。
・“掃除”の関係者
・鍵山秀三郎相談役と“掃除”について興味を抱いた人
・鍵山相談役から学びたい人
・掃除に興味のある人
こんな方々に確実に届く情報を発信していきたい。
そしてまだ掃除の可能性を知らない人や若い人たちに
情報を届けたく、“清風掃々”を
WEBマガジン化することになったというわけ。
既に掃除と取り組んでいる若いメンバーに
もっと活躍して欲しいという期待もあってのことだ。
さらに、鍵山相談役ももうすぐ米寿を迎えようとしている。
相談役から学んだ経営者も、相談役同様に年齢を
重ねている。今ここで、“掃除”をその先に繋げていくためにも
若返りが求められている。
次世代へバトンを渡すことも考えてのWEBマガジン発行なのだ。
このWEBマガジンは、
・相談役の本を読んだ人や相談役についてキーワード検索
してのアクセス
・冊子や他の紹介から、URL入手
・YouTubeや他のSNSとの連動
と様々な可能性があり、これからどんどん拡がっていくだろう。
(拡がっていかせたいわけだが・・・)
すでに掃除と取り組んでいる国も、
台湾、中国、イタリア、ルーマニア、アメリカ、インドと
世界に拡がっている。
一部を英語にするだけでも、可能性はどんどん拡がるということ。
すでにイタリアとやり取りをしていて、
イタリアからこのWEbマガジンに記事を
掲載してくれることになっている。
改めて、限定されていた人たちへのリアルの冊子配布から
オンライン化による効果は、その10倍の5万人以上、
もしかしたら100倍を超す50万人以上に拡がる可能性があるのだ。
SNSや検索による様々な人たちからの興味の拡がりを期待したい。
魅力あるマガジンとして発信することでより多くの方々に
見てもらえるようになっていくだろう。
高齢化が始まった“日本を美しくする会”も
次なる時代の“日本を美しくする会”にスタートを切ったということ。
魅力ある“清風掃々WEBマガジンONE by ONE”
掃除に興味のない“あなた”もぜひご高覧あれ!!
新たな気づきや出会いがあるかも!?