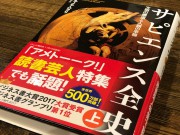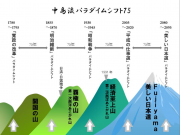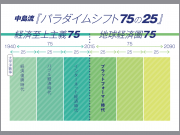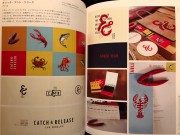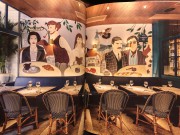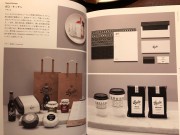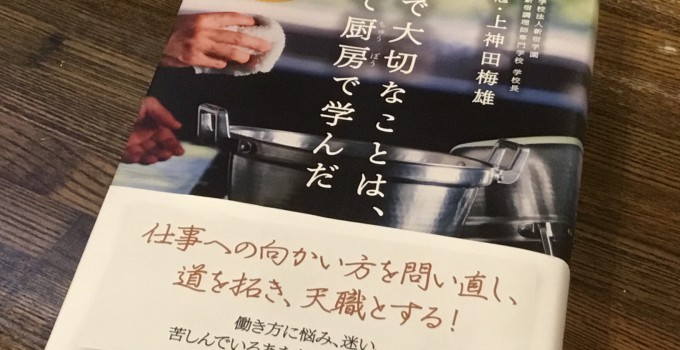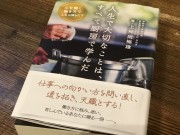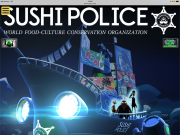11/05
2018
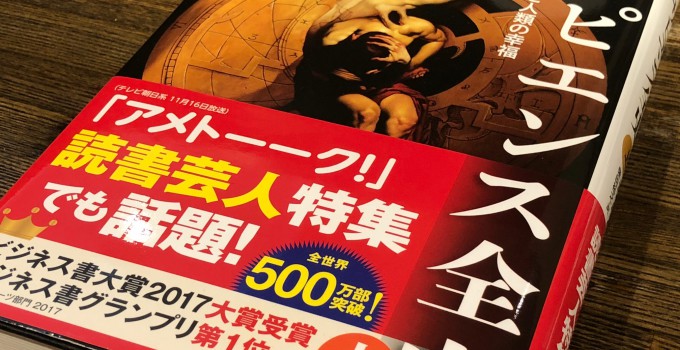
サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福
今回ご紹介する、『サピエンス全史』。
イスラエルの歴史学者である、
ユヴァル・ノア・ハラリが書いたもので、
現在とても話題となっている本だ。
本屋へいくと、まだまだ大量に平積みされているはず。
上下巻で構成されており、
実はまだ上巻の途中である。
だが、その内容から中島流の
ひとつの結論に至ったので、
その話をしようと思う。
この本についてだが、簡単に言うと
こんな内容だという。
(カバーに書かれているリード文より)
“ホモサピエンスが植物連鎖の頂点に立ち、
文明を築くことができたのはなぜか。
その答えを解く鍵は「虚構」にある。
虚構こそが、見知らぬ人同士が
協力することを可能にしたのだ。”
う~ん、わけがわからない!
まず、「虚構」がわからない!
虚構=現実でない世界をあたかも現実のように
“括った”概念だという。
さまざまな時代、場所で、
人はある“括り”に属することで協力し合い、
生存競争で生き残ることができるというのだ。
さて、私が注目した人類の歴史だが…
私たちのパーソナルスペースはだいたい4~5m。
真ん中をとって、4.5m=4500mmとしよう。
地球の誕生は、約45億年前とされている。
(4500mm=46億年とする)
ちょうどいいので、会議室のデスク周りを
地球の歴史と仮定してみたのだ。
それでいくと、アフリカで最初に
石器が発見され、人類の起源が
確認されたのが約250万年前。
人類の歴史は4500mmの2.5mmでしかない。
そこから、東アフリカでホモサピエンスが
進化したとされるのが20万年前。
誕生してからこの間、約0.2mmである。
そして、動植物の生命を操作し、食物とする、
いわゆる農業革命が1万2000年前。
わずか1/100mm=10ミクロンだ。
そして産業革命に至っては、200年前。
もはや…。
人類の歴史が広大なデスクなのであれば、
急速に進歩を遂げたのは、爪の先ほどもない、
目にも見えないほどなのである。
私が提唱するパラダイムシフト75では、
75年周期でパラダイムの転換期があるとしているが、
この75年だけを見ても
人類は凄まじい進歩をしている。
ITやAIなど、さまざまな技術が開発され
より一層進歩のスピードは加速しているのだ。
長い長い地球の歴史の中で、
私たちが今のカタチへと急激に進化した。
それは、1ミクロンにも満たない間なのだ。
次の75年はどんな進化を遂げるのか。
先のことが楽しみではありつつ、
人間たちは急ぎすぎているのではないか、
そんな気もしている。
私たちに関わりのある、はるか遠くを
思い起こさせてくれるサピエンス全史。
まさに私たちを“タテの発想”に導いてくれる。