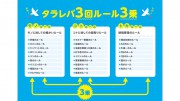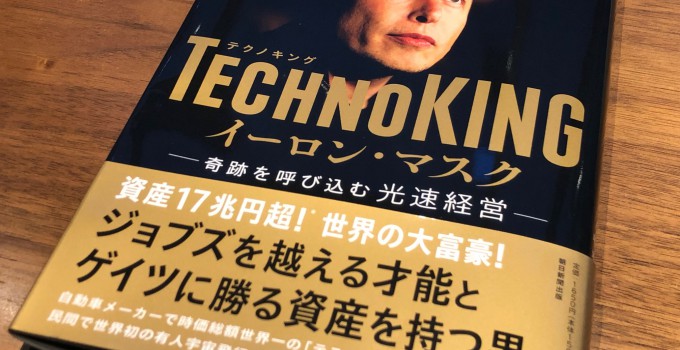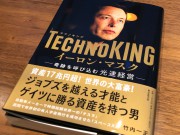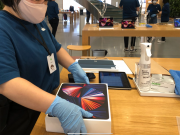11/08
2021
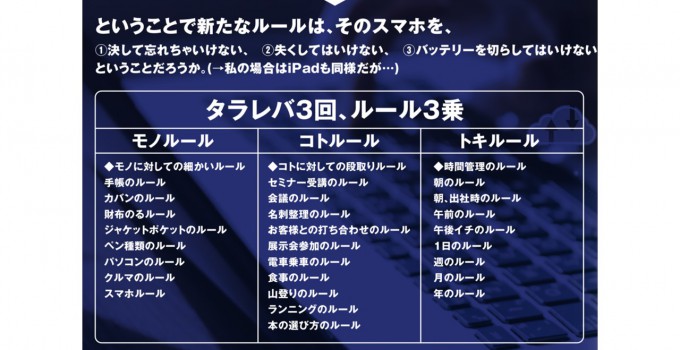
“タラレバ3回、ルール3乗”もDX化へ
先週のビジ達で触れた、“モノルール”、“コトルール”、“トキルール”
の元の概念が、“タラレバ3回、ルール3乗”だ。
あの時、○○していタラ…、○○していレバ…。
こんな風に「タラ」と「レバ」が出てくるシーンを3回くり返したら、
それをしっかりルール化するという概念。
目に見えないことを自分なりにルール化することだ。
そのポイントは、“モノ”と“コト”と“トキ”を
かけ合わせてルール化することで、
よりいいルールができることから、“3乗”となっている。
これを実践することは、ビジネスや日々の生活の中で効率化がはかられ
結果として質にも影響してくるということ。
(中島らしい分かりやすい概念だ・・・)
これは、拙著“非効率な会社がうまくゆく理由”でも紹介している。
その“タラレバ3回、ルール3乗”も、いまやDX化の
時代に入ったということだ。
すなわち、スマホの出現でそのルール化の方法が
変わろうとしている。
“タラレバ3回、スマホで3乗”ってな感じ?!
“モノルール”、“コトルール”、“トキルール”の内容については
概念図に詳しく記してあるので読んでほしい。
例えば、私の“高尾山登頂”においては、
山登りに必要なモノを持ち、
山登りの道順やチェックポイント(コト)があり、
そして参考タイム(トキ)もあるといい。
私の場合は、これらが明確になっているので、
過去と照らし合わせ(いつもより早いとか遅いとか、
息切れや疲れ具合など)より意味ある山登り体験に
つながるということ。
これら、“モノルール”、“コトルール”、“トキルール”
が今や、なんと全てスマホに集約されている。
すなわち、
→スマホのスケジュールを活用
→スマホのメモを活用
→スマホの連絡先を活用
→スマホの写真(アルバム)を活用
作ったルールのデータはあちこちに分散せずに
スマホに一本化し、DX化していくことで、
決めたルールがさらに活用され、振り返りも容易になった。
となると…スマホの紛失や、電池切れは
致命的なことになると気づき、
新たなルールは、そのスマホを、
1.決して忘れちゃいけない
2.失くしてはいけない
3.バッテリーを切らしてはいけない
ということ。(→私の場合はiPadも同様だが…)
そこで、新たなモノルールとして
背中のバッグには少し大きめのモバイルバッテリーを常に入れ
持ち歩くことをルールにした。
(山登りで遭難したときなどは、命綱となる…)
“くしゃみ3回 ルル3錠”から名付けた、
(ある程度の年齢の方ならご存知のCM)
“タラレバ3回、ルール3乗”もついにDX化する時代となり、
より確かなルール化が実現できるわけだ。
改めて、日々の生活やビジネスで
“タラレバ3回、ルール3乗”を実践してもらいたい。
それが結果的に“選ばれる”ことにもつながるということ。