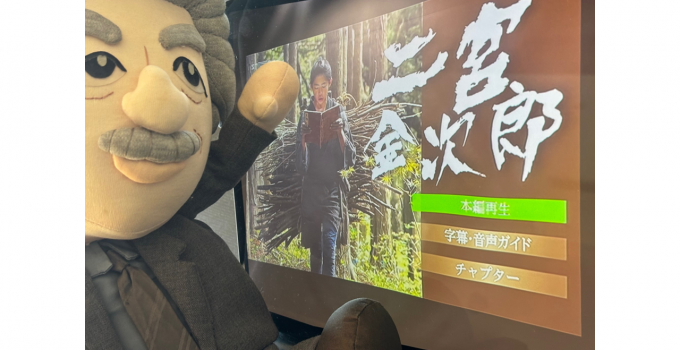03/31
2025

ホスピタルクラウン大棟耕介氏は、 “能登半島”被災地支援を続ける!
ホスピタルクラウン“大棟耕介”が
東北大震災の時も、熊本震災も、渦中のウクライナも
そして能登半島の復興支援でも活躍する。
被災地の人々に支援物資も携えての訪問だが、
なんといっても“クラウンK”こと大棟耕介は、
その地に“笑顔”を届けに行っている。
【珠洲市と輪島市へ、クラウンサーカスを届ける!】
この3月のある週末、このホスピタルクラウン協会の
大棟耕介氏率いる“能登半島の復興支援”に
同行させてもらった。
【1】珠洲市の仮設住宅近くの公園
【2】輪島市の小学校体育館
この2カ所での支援物資の提供とクラウンサーカスの開催。
(実は“ホスピタルクラウン”のみなさんは、
私たちが合流する前に
2カ所でクラウンサーカスを展開していたという)
このサーカスのテントづくりがまずの大仕事。
6角形のそれぞれの柱の元に2~3人の男性が必要で、
手間もかかるし、その手順も重要。
支援の初日は公園でのテントづくりで、
天気はよかったのだが、なぜか風の強い日。
これが慣れない私たちにとっては難敵となったのだ。
そして、サーカスに貢献できない私たちは、
さまざまな企業から提供された多くの支援物資の袋詰めが役割。
(まぁ少しは役に立ったと思うのだが…)
愛知県のある中学校からは、5人の中学生の弦楽器奏者と
引率の先生が2人参加し、いいパフォーマンスを展開していた。
(このパフォーマンスが、会場の人たちを優しい顔にしていた!)
とはいえ、“クラウンK”たちのそのパフォーマンスであり、
さまざまな出し物による“笑顔づくり”には、圧倒された次第。
(被災地におけるクラウンの役割りが見えてきたような?!)
【クラウンのパフォーマンスは、心に寄り添う特別な存在!】
実は大棟耕介氏とは、JC(青年会議所)時代からの
付き合いだから、もう30年経ったのかもしれない。
その頃は“クラウン”すなわち“道化師”として活躍していた。
ところが、病院の小児病棟での子供たちの笑顔づくり…
すなわち“ホスピタルクラウン”としても
活躍するようになってからは、国内だけでなく
世界の“クラウンK”となっていたのかもしれない。
クラウンのパフォーマンスは、困難な状況に直面する
被災地において、心に寄り添うことのできる特別な存在。
彼の訪問する場所には、必ず“笑顔”が伴う。
被災地では多くの場合、物資の不足やインフラの損壊が
注目されるが、心の疲弊や希望の喪失といった
見えにくい問題が大きな課題となっている。
“クラウンK”の笑顔づくりは、困難な状況を生き抜く力を
その地域の人たちに与えているということ。
すなわち笑顔や笑いは、多くの人々に
励ましを提供しているのだ。
また、彼の訪問は、地域コミュニティを再び結び付け、
人々が共に笑い合い、経験を分かち合う場を演出している。
“コミュニティの再生”を促進する役割も果たしているということ。
↓ ↓ ↓
改めて…クラウンとして“笑顔”を提供できない私たちは、
何をどうお手伝いしたらいいのだろうか?!
もちろんお金や物資の支援もあるだろう。
今回のように“クラウンサーカス”のサポートという
人的支援もあるだろう。
そして“ホスピタルクラウン協会”に寄付することもその一つ。
災害はいつか必ず訪れるもの。
だからこそ、互いに協力し合い支え合っていきたい。