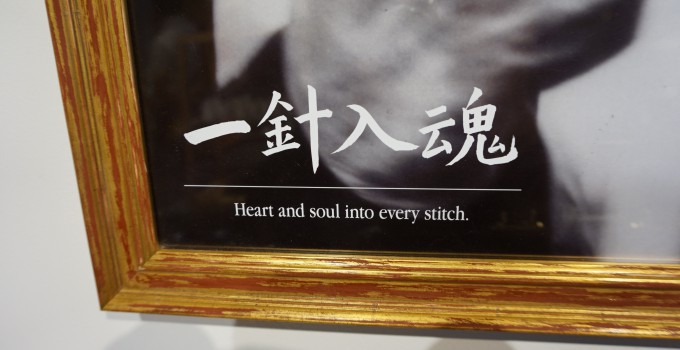08/03
2015

ラバーダックの仕事道
「わたしも何度か海外へ行った際には、
なかなかの吸引力を持っていたと思うけど…
しかし“ラバーダック”の吸引力には、
とてもじゃないけど敵わないなぁ」
多くの場所で活躍してきたMr.セイージ自ら(!?)
紹介してくれた、ラバーダック。
その名の通り、ゴム(=ラバー)のアヒルのことだ。
これは2007年にオランダ人アーティストである
フロレンティン・ホフマン氏によって制作された、
パブリックアート作品なのだが…。
よくお風呂の湯船に浮かんでいる、
黄色いアヒルを想像してもらいたい。
あのアヒルを、なんと12メートルもの大きさにしたものが、
今回お話させてもらう“ラバーダック”だ
(それぞれの国で制作されているため、
大きさや顔つきには違いがあるようだ) 。
実はこのラバーダック、世界中で大活躍しているそうだ。
この作品のコンセプトは、国境や人種に関係なく、
さまざまな人を癒し、喜ばせること。
作者の出身であるヨーロッパを始め、
南米、アジア、オセアニア、北米。
世界中の町の水辺で、その姿が披露されているのだ。
実際に子どもの頃、おもちゃのアヒルを
お風呂に浮かべたことがある人はもちろん、
映像や絵本でラバーダックの姿を知っている人も多いはず。
そしてなにより、マイナスのイメージを持つ人は少ないはず。
だからこそ、幸せや喜びの象徴として、あの黄色いアヒルを用いたそうだ。
わたしも自身をモチーフにした、
Mr.セイージという小さなぬいぐるみを各地に連れ立っている。
このMr.セイージでさえ、海外では思いがけない吸引力を発揮する。
「Oh! Looks like…(とても似ていますね)」
「What is this?(これ何ですか?)」
わたしを模したぬいぐるみのほうが、
わたしよりも注目の的になることが多いのだ。
その実体験をふまえてみると、
世界中を巡るラバーダックの吸引力は、絶大なのだろう。
日本でも2009年に大阪に登場し、一躍人気者となった。
そして今年、ついに東京にも訪れるかもしれない!
プロデューサーでありプランナーでもある
山名清隆氏とお話させていただく機会があったのだが、
その画策をされているそうだ。
人々の心の中でいつまでも生き続けてほしい、
そんな願いから常設展示はされていないものの、
世界のあちこちに出現する存在感は圧倒的だ。
これだけ多くの人を集め、
そして記憶に残り続けていく存在。
これぞ、ラバーダックの仕事道なのかもしれない!
そのラバーダック東京初登場を手がける
プロデューサー山名清隆氏がラジオに登場!
8/9・8/16放送の『BUSINESS LAB.』をお聴き逃しなく!
--------------------------------------------
InterFM『BUSINESS LAB.』
東京76.1MHz・横浜76.5MHz
毎週日曜 朝6時から好評放送中!