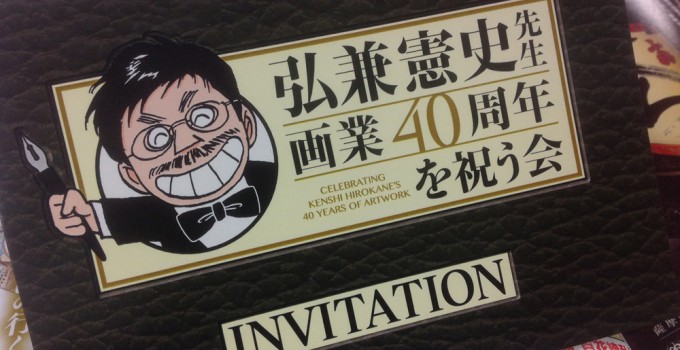12/08
2014
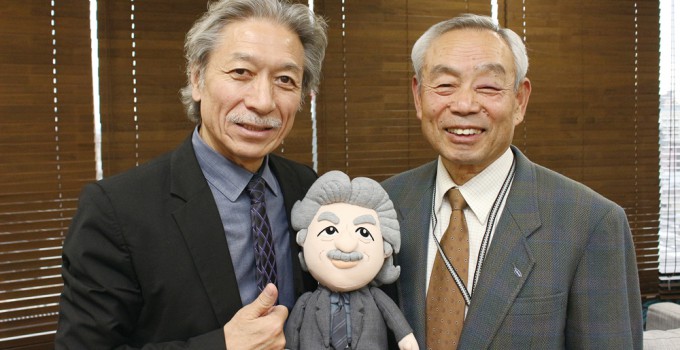
「久保工」の地域と共に仕事道
東京・神田に「株式会社久保工」という会社がある。
宮大工店から出発した建設会社だ。
神田だけでも500棟(スゴ~イ!)の
ビルを建てたというこの会社では、
現在ビル建設はもちろん、メンテナンス含めた
幅広いアフターフォロー業務を行っている。
私も所属していた青年会議所の先輩、
久保金司氏は、この会社の二代目社長を務めていた方だ。
青年会議所に31歳のときに参加され、
そこで社会奉仕活動に出会ったのだとか。
久保氏はその活動に深い感銘を受け、
その価値観はその後の久保工の経営にも
大いに生かされていったという。
その価値観とは、ずばり「地域と共に」というもの。
例えば、神田の小松川では交通事故が非常に多かった。
特に、幼児の痛ましい事故が多かったのだという。
そこで、地域のため、子どもたちのため、
久保氏を含むメンバーたちは立ち上がり、
様々な働きかけをした。
結果、小松川に交通少年団ができ、
事故件数を大幅に減らすことに貢献したという。
また、河川の公害問題に取り組み、
「多摩川をふたたびメダカの泳ぐ美しい川に!」
という思いから「ラブ・リバーキャンペーン」を
5年間にわたって行ったのも、社会貢献活動の一つだ。
こうした地域貢献、地域奉仕の姿勢は、
ボランティア活動だけにはとどまらない。
「神田ルネッサンス」というタウン誌作りを
主宰されていた久保氏は、そこで学んだこと、
出会った人をきっかけに、
「街づくり」を考えた建設業であり仕事のあり方を
考えるまでになった。
これは「神田学会」という、神田地域を盛り立て、
発展させるための勉強会の結成に結びつき、
現在も盛んな活動が行われている。
こうした地域貢献活動に対する久保氏の思いは一つ。
「地域が良くならないと、久保工も良くならない」。
地域を活性化させ、そこに暮らす人を幸せにし、
働く人にやりがいをもってもらい、
地域と共に会社を発展させる。
地域貢献の姿勢がない限り、
その会社は発展しないというのだ。
まさにまさに!
サステイナブルなビジネスを築き上げるためには、
自分の会社のことだけを考えていてはダメなのだ。
地域に貢献し、その地域と共に生きる会社でなくては!
そこで働く人、そこで関わる会社、
全てによくできる会社こそが、
結果として継続できるビジネスを展開できる会社になるだろう。
そんな久保氏の仕事道がたっぷり聞けるラジオ
BUSINESS LAB.は12月14日、21日(日)それぞれ朝6:00から!
ぜひぜひ聴いていただきたい!!