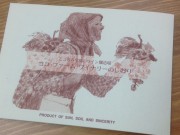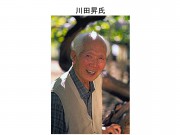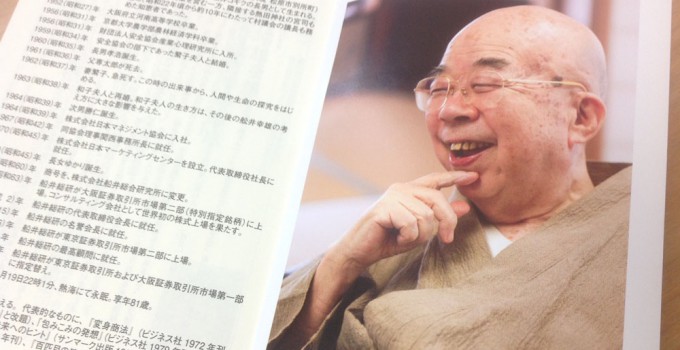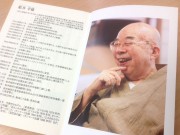07/22
2014

“永遠の中小企業”ホットマン
先日、日本を美しくする会で仲間を祝う会が開催された。
株式会社ホットマン(伊藤信幸社長)の
JASDAQ上場を祝う会だ。
東日本大震災以降、
東北に本社を置く企業としては初めての上場だという。
宮城県仙台市に本社を置くホットマンは、
イエローハットを中心にTSUTAYA、
ガリバー、セガなどの多くの企業店舗を
運営するメガフランチャイジー企業だ。
現在では宮城県・岩手県・福島県
茨城県・栃木県・長野県の6県で
100店舗以上を展開している。
伊藤社長によるキャッチフレーズは
「永遠の中小企業」。
常に未完成であり、時代の変化に対応できる
企業であることをテーマにしている。
驕ることなく、努力を続けていける
企業でありたいということだろう。
こうした思いが込められたフレーズなのだが、
その他にもホットマンの経営理念として、
「社員の成長なくして会社の発展なし、
会社の発展なくして社員のしあわせなし」
という言葉がある。
この社員の成長に欠かせないものとして
取り入れているものが「掃除」なのだという。
掃除によって地域社会に貢献し、
社員一人ひとりの人間的成長を手助けすることで、
会社全体も発展させていく。
ここに日本を美しくする会の
よい影響があることは言うまでもない
(いや、鍵山相談役の影響と言った方がいいかも…)。
伊藤社長は、「鍵山氏に出会ったところから、
人生もビジネスも大きく変わった」と
祝う会でも語っていた。
“掃除”に取組みながら店舗展開を続けてきたことが、
ホットマンの上場にも大きく貢献しているのだろう。
伊藤社長は祝う会の中で、
震災の時に日本を美しくする会の方々が
物資と気持ちの両面で篤い支援をしてくれたことに、
深い感謝をしていると仰っていた。
そこから、会社としても目標を持たなくてはいけないと思い、
上場という目標を立てたのだという。
そして、それがついに実現したわけだ。
祝う会に集まった人たちは、
業種業態の違う経営者中心の20人ほどだったが、
“掃除”という共通の価値観を持つもの同士の
イベントだけに、終始和やかな空気が流れていた。
“掃除”が結び付け、
触発し合っては成長していくこの縁に改めて感謝を!
同志を祝いつつ、自らの発展を誓った会だった。